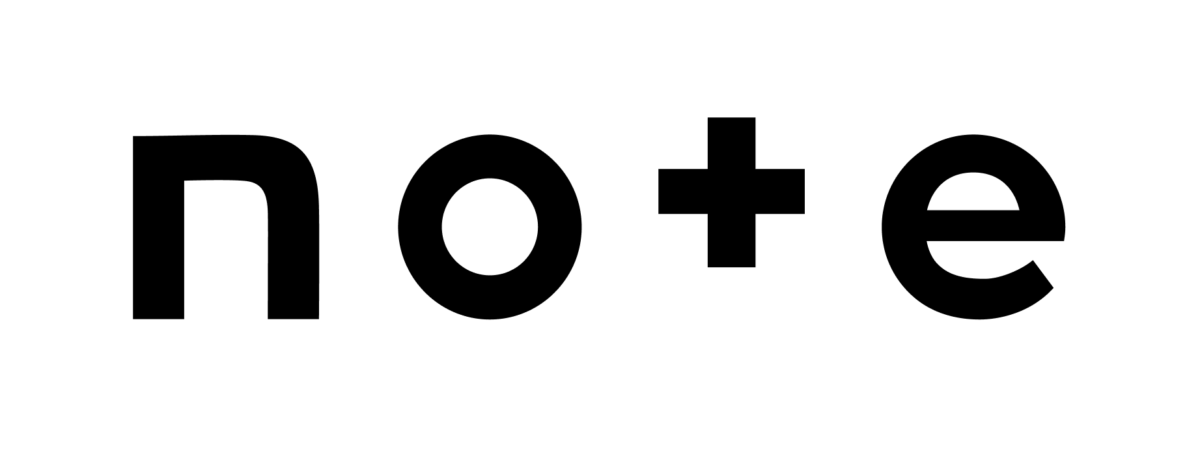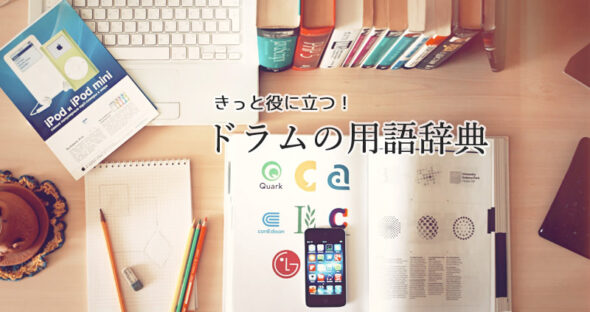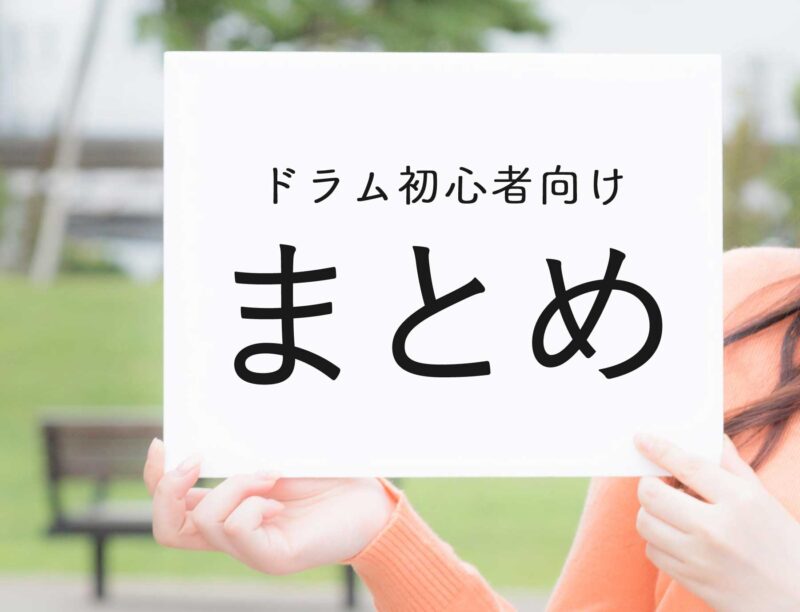ドラム教室のみっきーです。
個人レッスンや教則本でドラムレッスンをしてます。
Youtubeチャンネルもよろしくお願いします!
リズムの表現として、「表(おもて)」と「裏(うら)」という言い方があります。
リズムやグルーヴを語る上で、この「表と裏」はとっても大切です。
さらに、「裏拍」「裏打ち」「バックビート」など、似たような雰囲気たっぷりの言葉も頻繁に使用するので、初心者の方は大パニックになると思います。
…ということで、今回は「表・裏・裏拍」について、初心者向けに解説します!
目次
「表(おもて・あたま)」とは
表とは、リズムを感じる時に「1、2、3、4」と “普通に” 感じる所。これが表です。


これは4/4拍子の例です。
わかりやすく、シンプルで馴染みのある4拍子で話を進めていきますね〜。
「表」は何て読むの?
表は、「おもて」と言ったり、「あたま」と言ったりします。
リズムを指す場合は「おもて」という事が多いです。
しかーし!
実は、この「表(おもて)」という表現ってあまり使いません。
普通にリズムを感じることが「表を感じている」状態なので、あえて「表」という言葉を使った表現をする機会は少ないです。
「おもて」と「あたま」は違うの?
正直、厳密に使い分けて言うことはありません。右脳全開の「フィーリングで察する」って感じです。
ですが、経験上は拍を指して「頭(あたま)」とはあまり言いません。
通常、頭(あたま)は「最初の拍」「曲の一番最初」など、区切りの先頭部分を指す時に使います。
☞【関連用語】“あたま”とは
でも、表にスネアを入れるリズム・パターンは「頭打ち(あたまうち)」と言います。この辺がややこしいです。
☞【関連用語】“頭打ち”とは
頭打ちは、こんなパターンです↓

「表(おもて)」って本当に使わないなぁ。
次に解説する「裏(うら)」はすげー使う。
「裏」の話をしている中で「表」っていう言葉を使うことはあるかな。でも、それはあくまで「裏」の話の流れで使う感じ。
リズムパターンの会話の中では「頭打ち」って言葉はよく使いますので、要チェックです!
例:「サビは頭打ちでいこう!」…みたいな感じ。
「裏(うら)」とは
表に対して、「裏」というリズム表現(拍の表現)があります。
通常「1、2、3、4」と”表”で拍をとります。
それに対して拍の裏とは「1と2と3と4と」の様に、「と」の部分を”裏”といいます。

英語でカッコよく言うなら、「1 & 2 & 3 & 4 &」みたいな感じで、「&」の部分が裏。
「ワン. エン、ツー. エン、スリー. エン、フォー. エン」の「エン」の部分ですね。
「裏」は何て読むの?
裏は「うら」と言います。
それ以外にも、「裏拍(うらはく)」「拍の裏(はくのうら)」の様な表現をすることもあります。
どっちにしても「裏(うら)」がキーワードです。
裏という用語は、ドラムのレッスンでもバンド練習でもよく使います。
使用例:
- ここは裏にアクセントが入っているのかな?
- ここには裏でキメを入れよう!
- 16ビートのファンキーなグルーヴは、裏を感じて!
- ここの4拍目「裏」でクッてる所が、バラバラなので練習しようぜ!
☞【関連用語】“くう・くい”とは - このリズム・パターンは、バスドラムが裏に入っている所がカッコいいよね
裏拍(うらはく)とは?
新たなワード「裏拍」ってのが出てきました。ここがややこしい!
「裏」も「裏拍」も、大きくとらえれば同じ様な感じなのですが、リズムの会話の中では全然違う意味で使われる事が多いです。
裏拍とは、「1、2、3、4」と数える4分の4拍子のグルーヴにおける『2拍目と4拍目』を指します。
そう!8ビートとかでスネアを叩いてるあそこのことです!
(※実は、これは裏拍とは言わずに「バックビート」という事が多いです。後で説明しますのでちょっと待ってね。)
ジャズ、ロック、R&B…などのポピュラー音楽では、この裏拍(2と4)がとても重要!「ノリ」というか「グルーヴ」の根源とも言えますね。
というか、ハッキリ言って演奏から「裏拍」を感じられない演奏はダサい。演奏から裏拍を「感じられない」っていうのがポイント。
「裏拍を意識して叩きましょう!」「裏拍が大事!」って話はよく聞くと思うけど、問題の本質はそこじゃない。本質は「演奏から感じられるか」がポイント。

いくら頑張って「裏!裏!2!4!」と意識しても、演奏から感じられなければ意味がない。
むしろ「裏拍(2拍4拍)」を意識するせいで、逆に「表(1拍3拍)」が強調されちゃってる…っていうパターンはよくあります。
ちなみに、「裏拍=2拍4拍」というわけではありません。2拍4拍の意味でも使うし、前に説明した「裏(1と2と3と4と…の”と”の部分)」の意味で使うこともあります。
まあ「裏の拍」という大きな概念で理解しておけばよいと思います。「1,2,3,4」みたいに4分音符の大きな単位の話の中では、「2・4のことかな…」と思えばいいし、もっと細かい1拍の中の話をしていたら「表に対応する裏(1との”と”)のことだな」と思えばいい。(…と思う。これを言うを身も蓋もないけど…判断の基準は「経験」です!)
裏拍・バックビートって何?違いはあるの?
裏拍(ここでは”2拍4拍”の意味で使います)のことを「バックビート」ということもあります。
というか、2拍4拍のことはドラマー的には「バックビート」っていうのが一番わかりやすい。
”ドラマー的には”というのがポイントで、他の楽器の方がバックビートって言ってるかはわかりません。。。

普段、バンドメンバーと会話する時に何て言ってるんだろう?と考えてみると、「2拍4拍」って言ってる気がする。
でも、そもそも「2拍4拍」みたいな話をすることが無いなぁ…。
「もっと2拍4拍を…」みたいな話って、「オマエ、ノリが超ダサいよ!」「あんた、センスないね。」って言ってるようなもんだから、なんか言い出しにくいのかも。
先に説明した内容の繰り返しになっちゃうけど、「裏拍=2拍4拍」というわけではありません。
- 裏拍は2拍4拍の意味でも使います(この場合、バックビートという事が多いかも)
- 裏拍は単純に「裏(1と2と3と4と…の”と”の部分)」の意味で使うこともあります
とにかく、何かの基準(表 “おもて”)に対しての裏!って事で、大きな概念と考えておきましょう!
「表」は演歌で「裏」は欧米か!?/オンビート・オフビートの話
さて、もう一つ「オンビート」「オフビート」の話もしておかないと、このテーマが完結しません。
また新たな用語が出てきましたが、言いたいことは一緒です。
オンビートとは?/1拍3拍と思っておけばいいかな
「手拍子」を表でするか?裏でするか?で、雰囲気が全く変わります。
よく、日本人の手拍子は「1拍3拍だ」って話がでてきますよね。
4分音符の表(1拍、3拍)で手拍子をすると、ちょっと演歌調になります。

「1拍3拍」のノリは、民謡や演歌、盆踊りみたいなイメージですね。
そのため、JazzやRockなどのアメリカ味が強い音楽で「1拍3拍」のノリ・グルーヴを演奏しちゃうと「違う!ダサい!踊れない!」ってことになる。
これは、どっちが正しいというのではなく「文化」だと思います。逆に言えば盆踊りを「2拍4拍」のノリで演奏すると、「違う!踊れないわ!」ってなりますよね。
そんでもって、この「1拍、3拍」のことを「オンビート」と言います。
先のバックビートと同じで「オンビート=1拍3拍」だけではありません。これまた「表」のことをオンビートと表現することもあります。
なので、オンビートは「表」ってイメージで理解しておけばいいと思います。
まあ、正直言って「オンビート」ってのは話の中では使うことはありません。(英語だと使うのかしら?)

実はもう1つオンビートを使う場合があります。
それは、「リズムのグリッドラインにぴったり合わせる」という意味で使いケースです。
「オンビートで叩く」と言えば、リズムの拍にきっちり乗って叩いている状態を意味します。(でも、使ったことあるかな?…って感じです。。。)
オフビートとは?/2拍4拍と思っておけばいいかな
4分音符の裏(2拍、4拍)で手拍子をすると、欧米調(というかアメリカ?)になります。

そんでもって、この「2拍、4拍」のことを「オフビート」と言います。
AIのGeminiに聞いてみたら、こんなまとめ表を出してくれました↓
| 概念 | 意味(主として) | 強調される拍(4/4拍子の場合) | 特徴 | 代表的なジャンル(強調される場合) |
|---|---|---|---|---|
| オンビート | ①強拍・表拍にアクセントを置くリズム。②グリッドラインにぴったり乗る。 | 1拍目、3拍目 | 安定感、推進力、拍子の明確さ、楽曲の骨格 | マーチ、演歌、多くのクラシック音楽 |
| オフビート | ①弱拍・裏拍にアクセントを置くリズム。②グリッドラインからずらすこともある。 | 2拍目、4拍目 | 躍動感、グルーヴ、ノリ、独特の「タメ」や「スウィング」 | ロック、ジャズ、ソウル、R&B |
ロック、ジャズ、ブルース、ソウル、R&Bなど、多くのポピュラー音楽で「バックビート」として用いられるリズムが、このオフビートの代表例です。

ジャズ、ロック、ブルース…など、アメリカ由来?の音楽では、この裏拍・バックビート・オフビート(2拍と4拍)がマジで重要!
「ノリ」というか「グルーヴ」の根源で、『2拍と4拍に神が宿る』と言っても過言ではない!
「裏」がわからない?!
最近のナウなヤングは、裏でリズムをとることも多くなっていますが、裏でリズムを感じる機会が少ない方(世代?)は、ビシバシ裏がキマっているファンキーなリズムが苦手になりがちです。
裏の概念が全く無い人は、信じられないかもしれませんが「裏のリズムが取れない」です。
裏のリズムって「音楽の環境」で大きくセンスが変わるので、腰にグイっと来るリズムを浴びるほど聞いて踊って、体に染み込ませることが大切です。

表・裏・裏拍・バックビートの練習方法
さて、気になるのが「表」と「裏」を鍛える練習方法はあるのか?ってこと。
個人的には、それに特化した練習方法はない!と思います。
というのも、これは概念というか、文化というか、感じ方というか…、そんなテクニックじゃない話だと思っているから。
じゃあ、どうすれば!?
はい、それは
- たくさんの音楽・色々なジャンルの音楽を聞く!
- そして、踊りまくる!
これです。
踊るってのが大事。そもそもビートは身体が自然に動くもの・聞いてる人に身体を自然に動かしてもらうもの。もっと過激に言えば「俺のビートで踊れ!」「俺のビート最高だろぉ〜?踊れるだろぉ〜?」「俺のビートで腰がグッと動き出すだろぁ〜」と思って叩くもの?
そのためには、自分が踊ってみないと感覚はつかめないと思います。
別にダンサーの様に上手に踊る必要はありません。私もダンスは苦手なタイプ…。
でも、音楽に・グルーヴに身を委ねて、自然と足踏みしたり、手足が動いたり、手拍子したり、腰が動いたり、バイブスアゲアゲヒャッハーになったり…。
そんな、音楽と自分を一体化させて・没入して聞く=インプットをすると、自然といいグルーヴ=アウトプットにつながると思います。

基礎練習やテクニックは「思いついたことを正確に再現させるための手段・再現できる身体能力」です。
【アウトプットしたいこと × 再現できる身体能力】の掛け算って事を忘れずに!
まとめ|表と裏の理解はリズム感の第一歩
リズムにおける「表」と「裏」は、ドラムや音楽演奏をするうえで欠かせない基礎知識。
特に「裏拍・バックビート」は、楽曲のノリやグルーヴを支える重要な要素で、初心者に限らず上級者やプロまで、どんなレベルの人でもつまずきやすいポイントでもあります。
「グルーヴ」という概念で日々熱い議論が交わされているように、永遠に追い求め続ける課題なのかもしれませんね。
\基礎練習の必須アイテム/
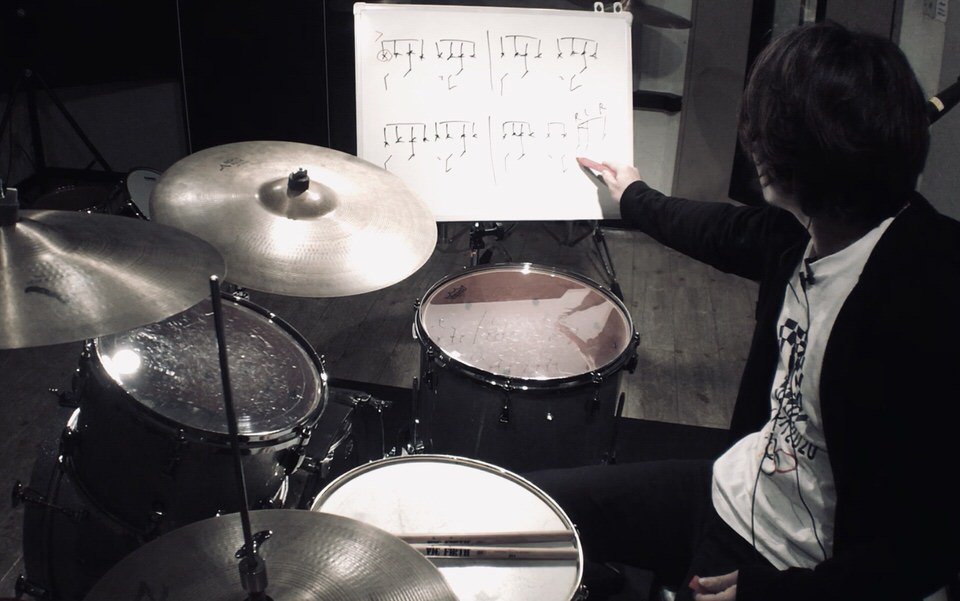
基礎からドラムを習う
ドラムを叩きたい!伸び悩んでいる...という方は、今すぐドラムの個人レッスンを!
基礎からちゃんと学びたい方にピッタリのドラム教室です。
\別館「note」もよろしく!/
独学で学びたい方は
- Youtubeでドラム講座
⇒ YouTubeチャンネル - 小ネタ・おすすめ動画をメルマガでお届け
⇒メルマガ登録はこちら - 教則本(練習パターン集)を販売しています!
⇒ドラムの練習帳:練習パッドで基礎練習編