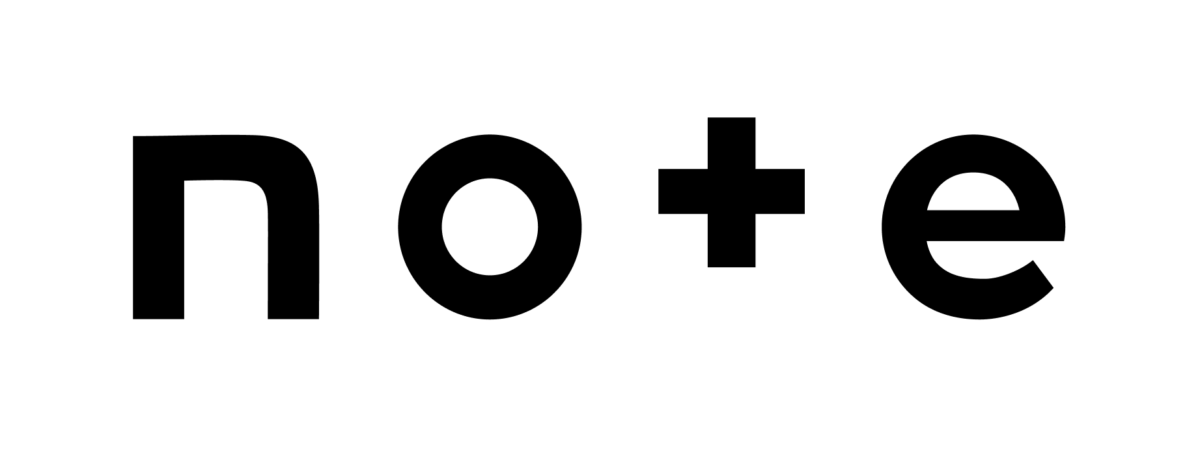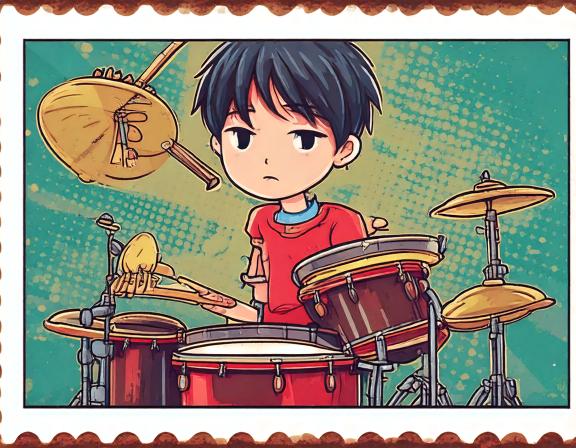ドラム教室のみっきーです。
個人レッスンや教則本もチェックしてね。
Youtubeチャンネル、Instagramもよろしくお願いします!
「ドラムを叩くと脳が若返る」とか「脳が活性化される」みたいな話を聞くことがあります。
私の肌感覚でも、やっぱりドラムって「脳トレっぽいな」と思います。手と足をバラバラに動かすし、感情も揺れ動く。まさに「心・技・体」を駆使して演奏しますよね。
とはいえ「本当にそうなの?!」って疑問もあるし、実際の研究ではどうなってるのか気になるところ。
という事で、今回は最近ハマっているChatGPT先生に「信頼性の高い論文から情報収集して!」とお願いした内容をご紹介します。(あくまでご参考程度にね。)ちなみにこの画像↓もChatGPTで作ってみました。
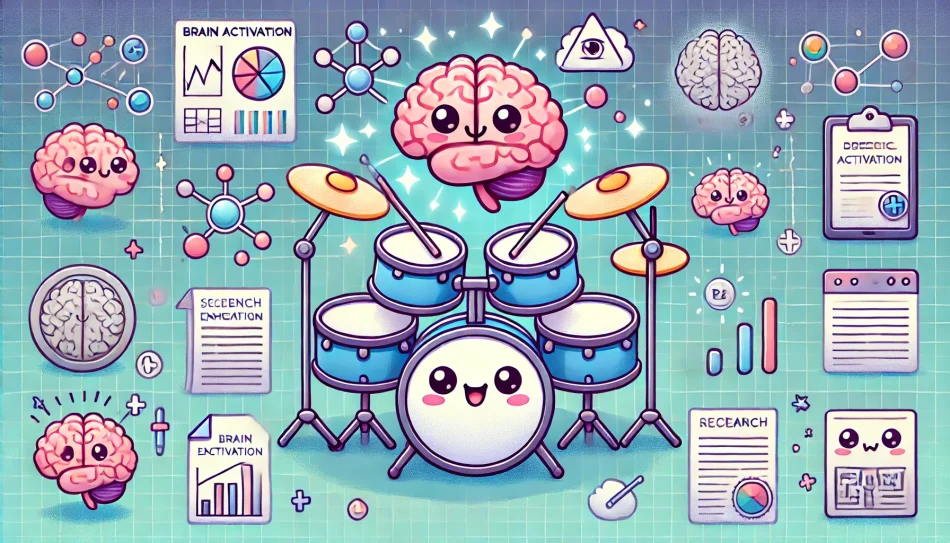
目次
ドラム演奏と脳の関係とは?
「音楽が脳に良い」という話はよく聞かれますが、その中でもドラム演奏が持つ影響については、特に注目されています。ドラムは単に音楽を奏でる楽器ではなく、両手と両足を独立して動かす必要があるため、運動機能や認知機能の向上に関わる可能性があると考えられています。
近年の研究では、ドラム演奏が脳の神経可塑性(Neuroplasticity)を高め、運動制御能力を向上させることが示唆されています。さらに、ドラム演奏が認知症予防や老化防止に役立つ可能性も指摘されています。しかし一方で、「本当にドラム演奏に特有の効果があるのか?」、「長期的に継続することでどのような影響があるのか?」といった疑問の声もあります。
そこで本記事では、ドラム演奏が脳に与える良い影響と、それに対する反対意見を、最新の研究をもとに詳しく解説していきます。
ドラム演奏が脳に与える良い影響
1. 神経可塑性を促進し、脳の構造を変化させる
私たちの脳は、一度形成されたら変わらないわけではありません。神経可塑性(Neuroplasticity)とは、新しい経験や学習によって脳の神経回路が再編成される能力のことを指します。これにより、私たちはスキルを習得したり、新しい情報を記憶したりすることができます。
近年の研究では、ドラム演奏が神経可塑性を促進し、脳の構造そのものを変化させる可能性があることが示唆されています。ドラムを演奏する際には、リズムを刻みながら両手両足を異なるタイミングで動かす必要があり、これが脳の広範な領域を刺激する要因となります。
では、ドラム演奏がどのように神経可塑性を高め、具体的に脳のどの部位に影響を与えるのか? 最新の科学研究をもとに詳しく解説していきます。
🎵 ドラムトレーニングによる脳の構造変化
神経可塑性とは、脳が新しい刺激や学習によって変化し、新たな神経回路を作る能力のことを指します。ドラム演奏は、両手両足を異なるリズムで動かしながらリズムを維持する必要があるため、脳の運動野や小脳が強く刺激され、神経可塑性が促進されると考えられています。
Bruchhage et al. (2020) の研究では、8週間のドラムトレーニングが脳の構造に与える影響を調査した結果、ドラム演奏者の脳では小脳(Cerebellum)と感覚運動皮質(Sensorimotor Cortex)の構造が変化し、運動制御能力が向上したことが確認されました。
📄 論文リンク
🧠 研究のポイント
- ドラム演奏が脳の神経回路を強化し、運動制御能力を向上させる
→ 複雑なリズムを演奏することで、異なる神経ネットワークが同時に活性化され、神経回路が強化される。 - 小脳や運動野が活性化され、リズム運動の習得がスムーズに
→ 小脳は運動の調整やバランス感覚に関与し、リズムを体で覚えることでその機能が強化される。 - 継続的なドラム練習が、脳の構造に長期的な変化をもたらす可能性
→ 一定期間の練習を続けることで、脳の可塑性が高まり、運動機能が持続的に向上する可能性がある。
2. 運動機能と認知機能の向上
🥁 両手両足を独立して動かすことが脳に与える影響
ドラム演奏では、右手でハイハットを刻みながら、左手でスネアを叩き、右足でバスドラムを踏み、左足でハイハットを開閉するなど、複数の動作を同時に行う必要があります。 このような協調運動は、運動能力の向上だけでなく、脳の実行機能(エグゼクティブ・ファンクション)やワーキングメモリの強化にもつながります。
Deyo (2016) の研究では、リズム運動が脳の運動制御ネットワークを強化し、運動能力の向上だけでなく、認知機能の改善にも寄与することが示されました。特に、認知症予防や神経変性疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病)のリスク低減に効果がある可能性が示唆されています。
📄 論文リンク
🧠 研究のポイント
- 手足を独立して動かすことで、脳のネットワークが強化
→ 異なる動作を同時に行うことで、前頭葉や小脳の神経回路が発達し、脳の処理能力が向上する。 - 認知機能の向上と認知症予防に役立つ可能性
→ ドラム演奏が記憶力や判断力を鍛え、認知症リスクの低減につながる可能性がある。 - パーキンソン病患者の運動制御能力の改善に有効
→ ドラムのリズムトレーニングが運動機能の回復を助ける可能性がある。
3. ドラム演奏が持つ「特有の」脳活性化効果
🎯 ドラム演奏特有の動作と脳への影響
ドラム演奏には、他の楽器には見られない特有の動作があり、それが脳の広範囲な活性化につながっています。
- ポリリズム(異なるリズムを同時に叩く)
→ 異なるリズムを各手足で奏でることで、脳の左右の半球が強く連携し、認知能力やリズム感が向上する。 - アクセントとゴーストノートの組み合わせ
→ 強弱のついた演奏が脳の注意力と感覚運動統合を刺激し、より精密な運動制御能力を養う。 - テンポの変化に対応する即興演奏
→ 瞬時にテンポを調整することで、脳の予測能力や意思決定能力が強化される。
📄 論文リンク
🧠 研究のポイント
- ドラム演奏は、他の楽器や運動と比べて特に左右の脳半球を連携させる能力が求められるため、認知機能やマルチタスク能力の向上が期待される。
- 「ポリリズム」や「即興対応」など、高度なリズム制御が必要なため、前頭前野や小脳の働きを強く活性化する。
- 運動能力だけでなく、思考力・判断力を同時に鍛えられる点が、他の楽器や運動とは異なる特徴。
1. ポリリズム(異なるリズムを同時に叩く)
ポリリズムとは、右手と左手、右足と左足がそれぞれ異なるリズムを奏でる演奏法のことです。
→ 例: 右手は8ビート、左手は16ビート、右足は4分音符をキープしながら、左足でハイハットを踏む。
📌 脳への影響
- 左右の脳半球を均等に刺激し、神経ネットワークを強化(Shaffer, 2022)
- マルチタスク能力や情報処理能力が向上
- リズムの整合性を保つことで、ワーキングメモリが鍛えられる
2. アクセントとゴーストノートの組み合わせ
アクセント(強く叩く音)とゴーストノート(小さな音)を織り交ぜながら演奏することで、手の微細なコントロールと感覚運動の統合が促される。
📌 脳への影響
- 運動野と感覚野の統合が進み、より正確な動作が可能になる
- 指先の動きが洗練され、細かい調整ができるようになる
- 触覚と聴覚の連携が強化される
3. テンポの変化に対応する即興演奏
ドラム演奏では、バンドのリズムをコントロールするために、曲の途中でテンポを微調整することが求められます。
📌 脳への影響
- 前頭前野(意思決定・計画を司る領域)が活性化
- 反射的な動作ではなく、意識的な調整が求められるため、認知機能が向上
- 判断力と反応速度の向上につながる
4.ドラム演奏の効果に対する反対意見
一方で、その効果について慎重に検討すべきだという意見もあります。特に、「ドラム演奏が本当に脳機能の向上や認知症予防に役立つのか?」という点については、まだ確立された結論が出ていません。
多くの研究は短期間の実験をもとに結論を導いており、長期間にわたる影響についてのデータは十分ではありません。また、「ドラム演奏に特有の効果なのか、それとも他の楽器や運動でも同じ効果が得られるのか?」という疑問も存在します。さらに、ドラム演奏が持つ脳への良い影響が、一部の人にしか現れない可能性も指摘されています。
🧠 ドラム演奏の長期的影響に関する研究不足
多くの研究がドラム演奏の短期的な効果を示していますが、長期間にわたる影響については、まだ十分な研究が行われていないという指摘があります。
例えば、Cahart et al. (2022) の研究では、ドラムトレーニングが認知機能を向上させる可能性を示唆しているものの、長期間継続した場合の影響や、効果が持続するかどうかについては明確なデータがないと報告されています。
📄 論文リンク
🛑 反論のポイント
- 長期間の研究が不足
→ ほとんどの研究は数週間から数か月のものが多く、長期間の影響は不明。 - 効果が一時的なものかどうか不明
→ 一時的に脳が活性化されても、演奏をやめた後に効果が持続するのかは未検証。 - 認知症予防における決定的な証拠はまだない
→ 直接的な因果関係を示す研究がなく、予防効果を断定するには不十分。
ドラム演奏特有の効果ではない可能性
ドラム演奏が脳に良い影響を与えるとされる一方で、「それがドラム演奏特有のものか?」という疑問もあります。例えば、ダンスやピアノなどの他の運動や音楽活動でも、同様の効果が得られる可能性があると指摘されています。
Shaffer (2022) の研究では、ダンスや音楽演奏による神経可塑性の向上が報告されていますが、それがドラム特有のものではなく、他の運動活動でも同じような効果が得られる可能性があることが指摘されています。
📄 論文リンク
🛑 反論のポイント
- ピアノやダンスなど他の活動でも同様の効果が得られる可能性
- ドラム演奏が特別に優れているとは限らない
- ドラム以外の音楽活動も脳の活性化に有効
ドラム演奏は脳トレになる?まとめ
ドラム演奏が脳に与える影響について、最新の研究をもとに解説しました。結論として、ドラム演奏は運動機能や認知機能を向上させ、神経可塑性を促進する可能性が高いことが示唆されています。
ただし、長期的な影響についての研究はまだ不十分であり、ドラム演奏が特有の効果を持つのかどうかは今後の研究が必要です。 しかし、楽しみながら脳を鍛える方法として、ドラム演奏は非常に魅力的な選択肢であることは間違いありません!
「脳トレ」としてドラムを始めるのも、良いアイデアかもしれませんね!
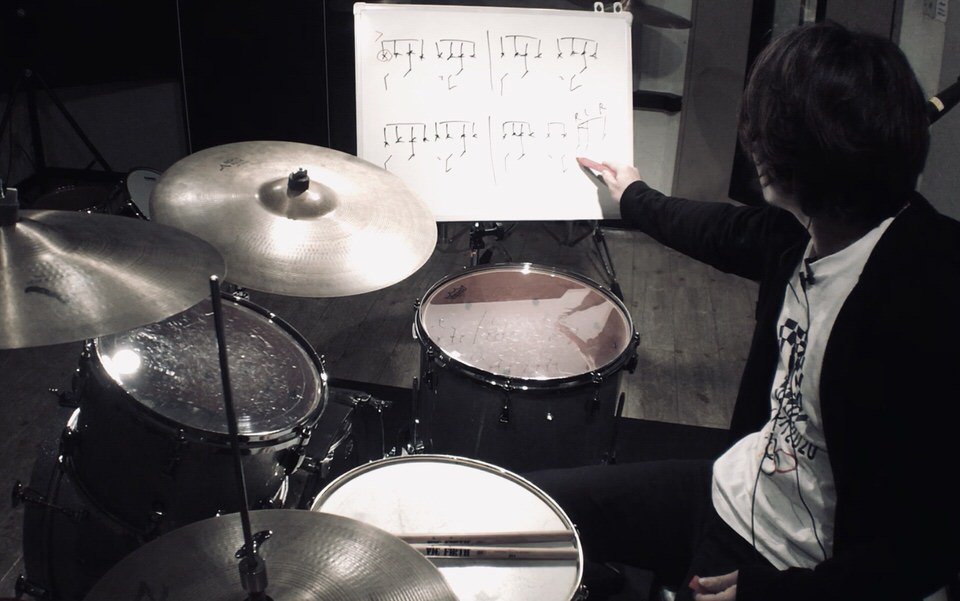
基礎からドラムを習う
ドラムを叩きたい!伸び悩んでいる...という方は、今すぐドラムの個人レッスンを!
基礎からちゃんと学びたい方にピッタリのドラム教室です。
\別館「note」もよろしく!/
独学で学びたい方は
- Youtubeでドラム講座
⇒ YouTubeチャンネル - 小ネタ・おすすめ動画をメルマガでお届け
⇒メルマガ登録はこちら - 教則本(練習パターン集)を販売しています!
⇒ドラムの練習帳:練習パッドで基礎練習編