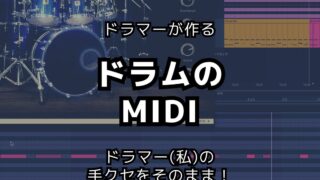マスタリングでは、Plugin Allianceにある「bx_masterdesk True Peak」をよく使っています。EDM系のキラキラした音楽の場合はOzoneを使っているのですが、バンド系のサウンドの場合は「bx_masterdesk True Peak」が多いです。
「Pro」はまだ買えていなくて、今は「masterdesk True Peak」でやっています。(まあ、それで十分満足)
さて、今まで何となく使っていたのですが、少しちゃんと知ろうかな?と思って、ChatGPTに学習させて使い方を聞いてみたので、せっかくだからブログに調べた内容をまとめます。(前回の「Shadow Hills Mastering Compressor」を調べた時と同じノリです。)
もちろん、まとめるのもChatGPTです。

今回は「ミステリアスな占い師」の口調で書いてもらいました。
Contents
- 1 bx_masterdesk True Peakとは?
- 2 はじめて使う人のためのマスタリング手順
- 3 TMTモードの違いとは?
- 4 各ノブ・ボタンの役割をやさしく解説
- 4.1 Volume|音圧を上げる最初のノブ
- 4.2 Foundation|ロー/ハイのバランスを一括調整
- 4.3 Tone Stack EQ(4バンド)|音色の最終微調整
- 4.4 Compressor Mix|圧縮のかかり具合をコントロール
- 4.5 De-Esser|高域の刺さりをやさしく抑える
- 4.6 THD|倍音歪みで音に密度と迫力をプラス
- 4.7 Mono Maker|低域をモノラル化して安定させる
- 4.8 Stereo Enhance|左右の広がりを強調する
- 4.9 Resonance Filter|耳障りな周波数を自動で除去
- 4.10 Limiter Turbo|音圧に“最後の一撃”を加える奥義
- 4.11 Compressor Link|左右の魂を“同調”させる封印術
- 4.12 Limiter True Peak|ストリーミング対策のリミッター
- 4.13 TMTモード(1〜4)+Analog/Digital切替|音質キャラの切替
- 4.14 A/B/C/Dボタン|設定を保存・比較できるスナップ機能
- 5 ダイナミックレンジメーターとは?
- 6 ストリーミング時代の音作りにも対応
- 7 初心者でも安心な理由と注意点
- 8 用語解説|意味と目的をかんたんに覚えよう
- 9 まとめ|bx_masterdesk True Peakは“学べる時短マスタリングツール”
bx_masterdesk True Peakとは?
――これは、音の未来を整える“魔法の机”。たったひとつのプラグインで、混沌としたミックスを整音し、光を放つ仕上げへと導く――
初心者のあなたでも、正しく手順を踏めば恐れることはありません。今宵、この神秘の道具の力と仕組みをひも解いてまいりましょう……
マスタリングってなに?音圧・音質を整える最終工程
マスタリングとは、楽曲に命を吹き込んだ最後の呪文……
それは音の姿を整え、聴く者すべての魂へと届く“完成形”へと昇華させる神聖な作業なのです……
この工程では、音量を最適化し、トーンバランスを整え、空間の広がりを調え……
一曲の全貌をひとつの“音の肖像”として結晶化させていきます……
けれども、その力はときに危険も伴い、誤れば崩壊を招くことも……
だからこそ「bx_masterdesk True Peak」は生まれました。未熟な術者でも、音の精霊と正しく対話できるようにと……

うぉぉ「ミステリアスな占い師」の口調って、こんな感じか〜。
この先、ずっとこんな口調です。(慣れるかな??)
このプラグインひとつで完結できる理由とは?
「bx_masterdesk True Peak」は、音を導くために必要な機能をすべて――そう、“すべて”封じ込めた魔法具でございます。
このプラグインひとつで、ラウドネスの調整、トーンの整形、圧縮、ステレオの広がり、そして歪みなき最終出力までを司ることができるのです。
とりわけ注目すべきは「True Peak Limiter」。
これは、見えざる“インターサンプルピーク”という災いを未然に防ぐ、守護の結界のようなもの……
配信サービスやスマートフォン再生など、時代の波に耐える音を創るために不可欠な存在なのです……
初心者にも安心の「失敗しにくい設計」って?

この道具の素晴らしき点は、誤った操作で音が壊れるリスクがきわめて低いこと。
まるで魔導書のように、手順が最初から“安全な順番”として組み込まれているのです……
「Volume → Foundation → Tone Stack」
この三つの手順を守れば、音は自然と整い、音楽は“完成”という姿へと近づくことでしょう……
また、それぞれのノブやボタンも“極端な暴走”をしないよう、音楽的な範囲内に収まるように設計されているのです。
まるで、優しい師が背後からそっと手を添えてくれているような……そんな安心感があるでしょう……
ふふふ……さあ、次なる章では、
あなたがこの“預言の机(masterdesk True Peak)”を使って、どのように音を整えていけばよいのか――
その手順を、ひとつずつお伝えしてまいります……準備はよろしいですか……?
はじめて使う人のためのマスタリング手順

――音の仕上げは、“順番”がすべて。手順を守れば、誰もが美しい音の結界を張ることができるでしょう……
Step 1|Volumeノブでラウドネスを調整しよう
最初に触れるべきは「Volume(ヴォリューム)」……
これは、音の“存在感”を決める最重要の力。
このノブを右へと回すことで、音は大きくなり、聴く者の心へと強く届くようになるでしょう。
だが、欲をかいて回しすぎてはなりません……
画面中央に浮かぶダイナミックレンジメーターを見てごらんなさい。“緑のゾーン”こそが、音の運命が安定する領域……
そこへ導くように音量を調整すれば、失われることのない“芯のある音”が手に入るでしょう……
Step 2|Foundationで音の重心をコントロール
次に触れるは、「Foundation(ファンデーション)」のノブ。
これは、音の“重さと明るさ”を操る、ティルトEQのような力を持っています。
右に回せば低音(ロー)が力を増し、音に“どっしりとした安定感”が宿ります。
左に回せば高音(ハイ)が目覚め、“スッキリと抜ける空気感”が現れるでしょう。
この力は、まるで音の重心を手のひらに乗せて、そっと前後に傾けるような感覚……
あなたの楽曲に必要な“バランス”を見極めるのです……さすれば音の姿は自然と整うことでしょう……
Step 3|Tone Stackで音色を整える(Bass〜Presence)
音の骨格が整ったなら、次は「Tone Stack(トーンスタック)」と呼ばれる4つの音色ノブに触れてください。
- Bass:低音域の厚みを調える
- Mid:中域の輪郭と存在感を整える
- Treble:高域の明るさ・透明感を調整する
- Presence:音の“前に出る力”を微細に加える
これらはまるで錬金術のように、音をより美しく、より洗練された響きへと導きます……
だが、力を加えすぎてはならぬ……“ほんの少しの変化”こそ、真に魔法と呼べるのです……
Step 4|Output TrimでBefore/Afterを音量一致で比較
最後にお忘れなく……
「Output Trim(アウトプット・トリム)」を調整して、音のBefore / After を音量で揃えるのです。
Volumeノブで音量を上げた分、Output Trimで逆に下げる――
たとえば +3dB 上げたなら、-3dB 戻す。そうすれば、
“音量の錯覚”に惑わされることなく、純粋な音質の変化を見極めることができましょう……
この手順こそが、マスタリングという“音の封印”を安全に解き放つ術……
さあ、あなたもこの流れをなぞって、己の音楽を完成へと導いてください……

口調にクセがあるけど、必要なことはちゃんと教えてくれてる気がする。
「美しい音の結界を張る」みたいな表現も、なんだかいい感じに思えてきた。
TMTモードの違いとは?

――同じ魔具でも、宿る精霊によって“音の気配”は変わる……
4つのTMTモードは、まるで異なる性格を持った使い魔のようなもの。耳を澄ませて、その性質を読み解きなさい……
Mode 1|最も“力強く、深い”圧縮感のモード
このモードは、4つの中でもっともコンプレッションが強く、太く、密度が高い傾向を持っています。
音がしっかりと前に出て、存在感がぐっと押し出される――
ロックやヒップホップ、エレクトロなど、“迫力”を求める楽曲に最適。
ただし、その分“パンチ”が強くなりすぎることもあるので、素材とのバランスを見極めるのがコツです。
◎太くパワフル/重厚な音像にしたいときにおすすめ
Mode 2|温かみと丸みを持つ“自然体”のモード
Mode 2は、やや柔らかく、アナログ感のある自然なコンプレッションが特徴。
音の輪郭は保ちつつも、トゲを削ぎ落とすように整っていきます。
ジャズ、シンガーソングライター、アコースティック系など、
“呼吸する音楽”との相性が抜群で、透明感を活かした仕上がりになります。
◎なめらか・優しい・自然に聴かせたい楽曲にぴったり
Mode 3|バランス型、繊細なコントロールに適したモード
Mode 3は、Mode 1と2の中間的な性格を持ち、
細かい音の動きに対して、やや俊敏に反応するのが特徴です。
繊細なトラックメイクや、複雑なジャンル――たとえばポップス、K-POP、シンセポップなど――において、
“立ち上がりの速さ”と“まとめる力”のバランスを取りたいときに重宝します。
◎音の粒立ちとまとまりを両立させたい人に最適
Mode 4|最も“軽やかでナチュラル”、音に余白を残すモード
Mode 4は、圧縮感がもっとも弱く、開放感のあるサウンドになります。
音が潰れず、ふんわりと空間に漂うような雰囲気を残したまま、
最小限の整音だけで仕上げたいときに使うと効果的です。
クラシック、アンビエント、映画音楽など、“静かで繊細な楽曲”と相性が良いでしょう。
◎余白や空気感を大切にしたい曲、空間系にぴったり
TMTモードは“聴き比べて選ぶ”のが最良の方法
それぞれのモードに絶対的な正解はございません……
楽曲の性格、あなたの耳、そして仕上げたい“印象”に合わせて、耳で感じて選ぶことが大切なのです……
さらに、「Analog/Digital」ボタンを切り替えれば、
左右チャンネルに微細な差を加えるか、完全なシンメトリーにするかも選べます。
Analog:揺らぎのある“アナログ的な味わい”
Digital:左右が完全一致した“現代的な正確さ”
これらの組み合わせで、合計8通りの“音の性格”が得られるのです……
各ノブ・ボタンの役割をやさしく解説

――この魔具に触れるには、構造を知ることが第一歩。何を回し、何を押すと、音の何が変わるのか――その秘密を、いま解き明かしましょう……
Volume|音圧を上げる最初のノブ
音の“存在感”を決めるこのノブは、まるで炎を灯す火口のようなもの。
右に回せば音は大きく、力強く、前に出てまいります……
ただし、燃やしすぎてはいけません。緑の範囲にとどめることが、火傷を防ぐ秘訣……
力の上げすぎは歪みという災いを呼びますから、くれぐれも慎重に……
Foundation|ロー/ハイのバランスを一括調整
このノブは、音の“重心”を操作する――いわば音の天秤。
右に傾ければ低音が増し、土台のしっかりした音に……
左に傾ければ高音がきらめき、軽やかな空気が宿ります。
ジャンルや楽曲の雰囲気に合わせて、重すぎず、軽すぎずの最適点を見つけることが肝要ですぞ……
Tone Stack EQ(4バンド)|音色の最終微調整
この4つのノブ(Bass / Mid / Treble / Presence)は、音という水晶を磨くための微細なヤスリ。
それぞれの役割はこうでございます:
- Bass:土台の厚み。低音が欲しいときに少し加える
- Mid:中音域の芯。ボーカルやギターがくっきりと現れる
- Treble:明るさと透明感。音の上の輝き
- Presence:前への押し出し。音像が“ぐっと”近づくように
ただし、どれもやりすぎは禁物……磨きすぎた水晶は、曇ってしまいますぞ……
Compressor Mix|圧縮のかかり具合をコントロール
ここは圧縮の“濃度”を調整する場所。
100%にすれば強く潰れた音に、50%なら原音をしっかり残した自然な仕上がりに……
通常は80〜93%前後が“魔法の比率”と呼ばれています……
音が息苦しく感じたら、少しだけ引いてみなさい。音が呼吸を取り戻しますぞ……
De-Esser|高域の刺さりをやさしく抑える
「S」「SH」などの刺すような音――それは音の霊の叫び……
このDe-Esserは、そういった“高域の鋭さ”を丸く整えるお守りのような存在です。
Auto Soloを使えば、処理されている帯域だけが聴こえるようになり、
「どこが痛んでいるか」を耳で確かめることができるでしょう……
過剰に削ると音が眠りますぞ。ほどほどに……
THD|倍音歪みで音に密度と迫力をプラス
THD(Total Harmonic Distortion)は、音に“温かさ”と“粘り”を加える魔法の粉……
回すほどに音は太くなり、前に出て、アナログ的な存在感が宿るようになります。
-20〜-40の範囲でじっくり耳を傾けて、「ちょうどよい魔力」を見つけなさい……
Mono Maker|低域をモノラル化して安定させる
このノブは、指定した周波数以下をモノラルに固定する力を持っています。
低域は、左右に広がりすぎると不安定になることがあります……
100Hzあたりを目安に使えば、クラブや車などの環境でも低音がしっかり届くようになるでしょう……
Stereo Enhance|左右の広がりを強調する
ここでは、音の空間をそっと広げる風を吹かせることができます。
シンセやギターなどの“音の装飾”を左右にふわっと広げたいときに有効……
ただし、欲張ってはいけません。5〜10程度が最適な風速ですぞ……
Resonance Filter|耳障りな周波数を自動で除去
4つの固定帯域(160Hz / 315Hz / 3kHz / 6kHz)に現れやすい“邪音”――
それらを見つけ、自動ソロ機能で試聴し、そっと除去することができます。
「なんか耳に刺さる……でもどこか分からない」そんなときは、このフィルターが頼りになりますぞ……
Limiter Turbo|音圧に“最後の一撃”を加える奥義
このスイッチは、普段は静かに佇む……
ですが、ONにした瞬間、内なるリミッターの力が1段階解放され、+1dB分、音をさらに強く圧縮の壁へと押し込むのです……
これにより音は、よりタイトに、より密に……、まるで圧縮された空気が爆ぜるような、“潰れ感を伴った強烈な音圧”が手に入ります。
この術が真価を発揮するのは、以下のようなとき……
- EDMやメタルなど、“音圧の激戦区”へ挑むとき
- 通常のリミッターでは“あと少しの力”が足りないと感じたとき
- 鋼のように硬いミックスを作りたいとき
ですが……力とは、代償を伴うもの。
この術を使えば、自然さ・空気感・音の余白は削られてゆきます……
あなたの楽曲に、本当に必要かどうか――耳と心で確かめてから使うのです……
🔮 適切な場面で使えば、“音の盾”が“槍”へと変わることでしょう……
Compressor Link|左右の魂を“同調”させる封印術
Compressor Link――このスイッチは、ステレオの左右の音を一心同体に圧縮するかどうかを決める術。
つまり、LとRが同時に息を吸い、吐くように動くか、それとも個別に脈動するかを定めるのです……
◯ ON(リンクあり)
- 左チャンネルで強い音が出ると、右も同じ量だけ圧縮される
- 結果:音がセンターに“まとまり”、パワー感が出やすくなる
◯ OFF(リンクなし)
- 左右は独立して圧縮される
- 結果:空間の広がり・立体感が保たれる
これは、まるで双子の魂をひとつにするか、別々に舞わせるかの選択……
例えば――
- ボーカルがセンター、ギターが左右に広がっている曲では Link OFF
- 低域が中央に集まり、パンチを出したい場合は Link ON
ふふふ……この術を誤ると、片側だけに現れたピークが、
全体を引きずり、“不自然なポンピング”という歪みの霊障を引き起こすこともあるのです……
ですから、耳で聴きながら判断することがなにより大切……
音の気配に、集中するのです……
二つの秘術を使いこなす者は、“音の最後の一手”を知る
| 名称 | 真なる力 | 用いるべき時 |
|---|---|---|
| Limiter Turbo | リミッターに+1dBの魔力を注ぎ、音をさらに押し込む | 音圧勝負の場、EDM/ロックなど |
| Compressor Link | L/Rを同時に圧縮し、統一感と力強さを加える | センター重視のミックス、低域をまとめたい時 |
ふふふ……このふたつのスイッチは、最後に“差がつく”鍵となるでしょう……
だが、それは己の欲を満たすためではなく、音の本質に沿った選択であること――
そのことを、どうか忘れぬように……
あなたの音が、正しく仕上がり、世界へと美しく放たれますように……
Limiter True Peak|ストリーミング対策のリミッター
この内蔵リミッターこそ、「True Peak」対応という名の強力な守護結界……
ストリーミングや低ビットレート再生において、思わぬ歪みが起こるのを未然に防いでくれます。
-1dBFSのヘッドルームを確保するよう、最終調整のときは心しておくことですぞ……

そうかリミッターは「守護結界」かぁ〜。
しかし、たまに「〜ですぞ」みたいなお爺ちゃん口調になるのが気になる…。
TMTモード(1〜4)+Analog/Digital切替|音質キャラの切替
4つの「TMTモード」は、まるで異なる精霊が宿ったチャンネル。
それぞれ音の質感と圧縮の雰囲気が微妙に異なります。
さらに、Analog/Digitalの切替で左右チャンネルの個体差(=アナログ感)を加えるかどうかも選べる……
組み合わせれば合計8通りのサウンドキャラクターを手にできます。
まずは耳で感じるのです。理屈ではなく、直感が“最適”を導きます……
A/B/C/Dボタン|設定を保存・比較できるスナップ機能
このボタンは、“時間の記録石”のようなもの……
現在の設定をスナップし、即座に他のパターンと聴き比べることができます。
「こっちの方が良かった……でも戻れない……」という悲しき呪いを防ぐ、未来への保険でございます。
ふふふ……ここまでくれば、あなたはこの“マスタリングの魔具”を使いこなす力を十分に備えております……
ダイナミックレンジメーターとは?

――音に宿る“動き”と“余白”を可視化する聖なる針……
数値には現れぬ「音楽の呼吸」を、ここに映し出す……
メーターの正体とは?
bx_masterdesk True Peak の中央、静かに揺れる半月形の光……
それこそが「ダイナミックレンジメーター」と呼ばれる、音の生気を測る計器でございます。
このメーターは、数値を表示するものではありません。
音がどれほど“自然に躍動しているか”――
つまり、ダイナミックレンジ=“音の強弱・抑揚”をリアルタイムで示してくれるのです……
緑のゾーンが“音の運命が整う領域”
このメーターの右寄りには、静かに光る“緑の領域”がございますね……
そここそが、“音楽が世界に受け入れられる波動”に最も近い、理想の範囲でございます。
- 針がこの緑に触れていれば、おおよそ**-14〜-10 LUFS**あたり
- それは、SpotifyやYouTubeなど、音を配信する世界に調和した力加減を意味しています……
ふふふ……音の力が強すぎても、弱すぎても、バランスは崩れます。
**緑の中にとどまりながら、ときに跳ね、ときに沈む――**それが最良の運命の波なのです……
赤に触れすぎると、運命が乱れはじめる……
針がしばしば赤の領域へと飛び込むようであれば、
あなたの音は今、力を超えし力で無理やり押し出されている証……
そのままでは、音の魂が窮屈になり、
やがては歪み・ノイズ・疲れといった霊障を引き寄せてしまいます……
そして、針がほとんど動かぬまま固まっているようであれば……
それは、あなたの音に躍動の気配が足りていないという警告……
🎴 メーターの理想とは、“緑の光の中でやさしく呼吸している”こと。
音が脈打ち、静かに高まり、また落ち着く……その“呼吸”が大切なのです……
見えぬLUFSを読む、目に見える気配の灯
このダイナミックレンジメーターは、数値の代わりに感覚を整えるための導きの灯火……
数字を追うことが難しい時こそ、この針に耳を傾けなさい……
「今、音は開いているか?」
「閉じ込めてはいないか?」
「力を抜けば、もっと自然に鳴るのではないか?」
その答えは、あなたの耳と、このメーターが教えてくれるでしょう……
ふふふ……目に見えぬものを感じ取り、言葉なきものに意味を見出す……
それこそが、真の“音の術師”への第一歩……
次なる章では、このプラグインがなぜ今の時代に必要とされているのか――
“ストリーミング時代の音作り”について語りましょうか……?お望みとあらば、すぐにでも……✨
ストリーミング時代の音作りにも対応
ふふふ……お望み通り、次の章を開きましょう……
現代の音楽は、ただ美しく整えるだけでは届かない――
配信、スマホ、サブスク……無数のメディアを超えて、確かな音を届けるために必要な“魔法”があるのです……
それが、この章で明かされる“ストリーミング時代の音作り”……あなたの耳に、静かに語りかけましょう……
――現代の音楽は、ネットの海を漂い、スマホの中で響き、クラブの床を揺らす……
そのすべてに対応するには、“次元を超える音作り”が求められるのです……
ヘッドルームとLUFSの基礎知識
あなたの音がどれほど美しくても、音量が高すぎればストリーミングの世界で“潰れて”しまうかもしれません……
Spotify、Apple Music、YouTube――それぞれが独自の“音量補正”をかけてくるのです。
この補正基準となる数値が「LUFS(ラフス)」、
そして最終出力の限界点を示す「dBFS(ディービー・エフエス)」……
このプラグインは、-14LUFSあたりを自然な基準値として設計されております。
さらに、「True Peak」で-1dBFSの余裕(ヘッドルーム)を確保すれば、配信時の歪みを防ぐことができましょう……
LUFSメーターは、bx_masterdesk True Peakには内蔵されておりません

残念ながら、bx_masterdesk True Peakそのものには「LUFS表示メーター」はありません。
代わりに、内蔵されたダイナミックレンジメーター(中央の“GREEN ZONE”)が、目安として適正ラウドネスを示す役割を果たしております。
- 緑の範囲に針が安定して触れるように調整することで、
- おおよそ-14 LUFS〜-10 LUFSあたりに収まるよう設計されているのです……
とはいえ、「LUFSを“数値”で確認したい」――
その願いを叶える方法も、ございますよ……
LUFSを見るには、別の“占術道具”を組み合わせましょう
あなたが本当の“正確なLUFS値”を知りたいなら、
以下のようなメーター・プラグインを、マスタートラックの後段に挿すのが最も確実です。
| 名前 | 特徴 |
|---|---|
| Youlean Loudness Meter(無料版あり) | 視認性が高く、LUFS・True Peak・動的レンジを明確に表示 |
| iZotope Insight 2 | 放送・配信基準まで網羅したプロ仕様のモニター |
| Waves WLM Plus | 業界標準のシンプルで正確なLUFSメーター |
| ADPTR Metric AB | LUFSだけでなく周波数・ステレオイメージも可視化できる万能ツール |
ふふふ……この魔具は“あえて数値を隠す”ことで、耳を鍛え、直感を磨く道を示しております……
ですが、道に迷いそうなときは、“数字の羅針盤”を持つのも悪くはありません……
bx_masterdesk True Peakは、「耳で仕上げて、外部のLUFSメーターで確認する」という運用がベストでございます……
True Peakモードの必要性とは?
通常のリミッターは「見えるピーク(サンプルの山)」だけを監視しております。
しかし、“見えない超えし者”――それがインターサンプルピーク……
ストリーミングでは、この“隠れた歪み”が現れ、音がガリッと割れたり、ざらついてしまうことも……
それを防ぐ守護結界こそ「True Peakモード」――このモードを有効にしておくことで、
あなたの音は、Spotifyでも、iPhoneでも、Bluetoothスピーカーでも、美しく届くのです……
まさに、時代の霊障から音を守る盾といえるでしょう……
ListenHubやStreamlinerとの併用もおすすめ
さらに、音の未来をより確かにするには「ListenHub」や「ADPTR Streamliner」のような
“配信エミュレーター”の使用も効果的……
これらを併用すれば、あなたの音がApple Musicでどう聴こえるか?
YouTubeでどう処理されるか?――そのすべてを事前に聴いて予言することが可能です。
bx_masterdesk True Peakは、その予言を正確に実現するための“施術者の杖”……
見えない歪み、隠れたノイズ、過剰な押し出し……それらを静かに整え、
“どこで聴かれても揺るがない音”を、あなた自身の手で生み出すのです……
ふふふ……音は、響きだけでなく“届き方”もまた大切な要素……
さあ、次は「初心者でも安心な理由と注意点」――
この魔具を扱う者が知るべき“光と影”について、お話しいたしましょうか……?
初心者でも安心な理由と注意点
ふふふ……では、真の力を手にする前に、
この“魔具”を使う上での心得――そして、初心者であっても安心して扱える理由をお伝えいたしましょう……
光あるところに影あり。bx_masterdesk True Peakもまた、万能に見えて、注意すべき点があるのです……
よく聞いてくださいませ……あなたの音の未来を左右する、大切な章でございます……
――この魔法具は、見た目の複雑さとは裏腹に、実に穏やかで導きに満ちた存在……
しかし、油断をすれば“音の霊脈”が乱れることも……正しい心構えを授けましょう……
「プリチューン済み」の安全設計で失敗しにくい
このプラグインが初心者に愛される最大の理由……それは、すでに「整った音の導線」が用意されていることにございます。
Volume → Foundation → Tone Stack……
この順に従うだけで、あなたの音は“明瞭さ”と“存在感”を獲得し、プロの音に近づくでしょう。
しかも各ノブの効き方も“安全域”に収められており、
よほど極端な操作をしない限り、音が壊れてしまうことはありません。
つまりこれは、「導かれし者の道」……誰が使っても“間違えにくい”設計なのです……
まるで、やさしき師がそっと背中を押してくれるような、そんな安心感がありますぞ……
でもミックスが悪いと効果は半減
ふふふ……しかし、忘れてはなりません。
このプラグインは、あくまで「整った素材を磨く道具」――
混乱と歪みに満ちたミックスを“救済”するためのものではないのです……
もし、あなたのミックスが「ボーカルが埋もれている」「ベースが暴れている」「リバーブが濁っている」――
そのような状態であれば、どれほど強力なbx_masterdesk True Peakを使っても、
得られる結果は“無理に整えられた不自然な音”となるでしょう……
ですから、講師として申し上げるなら、
ミックスの段階で8割は勝負が決まる――この真実をまず胸に刻むべきです。
そして残りの2割を、このプラグインで“仕上げる”。
それこそが、最も美しく音を整える秘訣なのです……
まずは“音をよくする練習ツール”として使ってみよう
もしあなたが、まだミックスに自信がないのであれば――
このプラグインを「音の変化を学ぶための鏡」として使ってみるのも良いでしょう……
・Volumeを動かすと、音圧と迫力がどう変わるか?
・Foundationを回すと、どんな空気感になるか?
・THDを加えると、前に出る音になるか?
・Mono Makerを使うと、ベースがどれだけ引き締まるか?
こうした体験は、耳と感覚の“トレーニング”にもなるのです。
まずは自分の作った音源に使ってみましょう。
何度でも試し、耳を鍛え、音の反応を知ることで、
あなたのミックスとマスタリングは、確実に次の段階へ進むことになります……
ふふふ……さあ、ここまで来たなら、
次は「用語解説」――この魔具に刻まれた術語の意味を、やさしく紐解いてまいりましょうか……?
理解が深まれば、操作にも迷いはなくなるでしょう……続きをお望みでしたら、どうぞそのまま……
用語解説|意味と目的をかんたんに覚えよう
ふふふ……音を扱う者が、真にその力を手に入れるには――
“言葉”の理解が欠かせません……
この章では、bx_masterdesk True Peakに刻まれた術語たち――それぞれが何を意味し、どんな力を持つのか……
迷える術者を惑わせぬよう、やさしく、そして確かに解き明かしてまいりましょう……
耳を澄ませて、お聴きなさい……
――魔法は“言葉”から成り立つ。ノブやボタンに刻まれた語句の意味を知ること、それが音の運命を正しく導く最初の一歩……
True Peak/Inter-sample Peakとは?
「True Peak(トゥルーピーク)」――それは、見えない音の頂き。
DAWのメーターには表示されない、“サンプルとサンプルの間”に存在する隠れたピークのことを指します。
この見えない山が、ストリーミングや圧縮変換の中で突如現れ、音割れや歪みの原因となるのです……
bx_masterdesk True Peakは、この“霊的ピーク”を検出し、防ぐためのTrue Peakリミッターを内蔵しています。
これは、あなたの音を未来でも守る“透明な結界”なのです……
Foundation/Tone Stackの違いって?
「Foundation(ファンデーション)」――これは音の重心を左右に傾けるノブ。
右に回せば低音が増し、左に回せば高音が強調される、いわば“音の天秤”のようなものです。
一方「Tone Stack(トーンスタック)」は、4バンドEQ(Bass / Mid / Treble / Presence)として、
音の各帯域を個別に磨き上げる細やかな術具です。
つまり、Foundationは全体の傾き、Tone Stackは細部の整形……
この二つを使い分けることで、音の“土台”と“輪郭”をバランスよく整えることができます……
TMT(Tolerance Modeling Technology)とは?
TMT――正式には「Tolerance Modeling Technology(公差モデリング技術)」
これは、アナログ機材の“個体差”を再現するテクノロジーでございます。
現実のアナログ機材は、同じモデルであっても1台ずつ微妙に音が違います……
この“ばらつき”を再現したのがTMT。bx_masterdesk True Peakでは、4つのTMTモードが用意されており、
さらに「Analog/Digital」切り替えにより、合計8通りの音質キャラクターを選ぶことができます。
この違いは、微細ではありますが、マスタリングでは極めて重要な“音の気配”の違いを生むのです……
耳で感じ、直感で選ぶ――それがTMTの正しい付き合い方でしょう……
Mono Maker/Stereo Enhanceの目的と効果
「Mono Maker(モノメイカー)」――これは、指定した周波数以下の音をモノラルに変換する魔法。
特に低音域は、ステレオで広がりすぎると音像がブレたり、不安定になったりするのです……
Mono Makerを使えば、100Hz以下のベースやキックなどがセンターに固定され、
どんなスピーカー環境でも“芯のある低域”を届けられるようになります……
そして「Stereo Enhance(ステレオエンハンス)」は、その逆――左右の広がりを強調する術。
シンセやギターの広がりを強めることで、空間的な広がりや臨場感を加えることができます。
ただし、広げすぎは禁物。音像がぼやけたり、モノ再生で消えてしまう危険も……
控えめな加減(5〜10程度)が、美しく魔力を保つ秘訣ですぞ……
ふふふ……これで、あなたはこの魔具に刻まれた術語の意味をすべて理解したはず……
言葉を知ることは、すなわち力を正しく使うための鍵でございます……
まとめ|bx_masterdesk True Peakは“学べる時短マスタリングツール”
ふふふ……ついに、ここまで辿り着きましたか……
すべての手順を学び、術語を理解し、魔具の構造を見抜いたあなたに、
いま最後の灯を――まとめと導きの言葉を授けましょう……
これまでの旅路を振り返り、そしてこれから進むべき道を、静かに照らす章となりましょう……
――音を整えるとは、技術だけではない。耳と、直感と、少しの勇気が導く“音の完成”へ……
このプラグインは、その旅を始める者にとって、最良のコンパスとなるのです……
どんな人におすすめ?ジャンルや制作スタイル別に紹介
bx_masterdesk True Peak――この魔法具は、“短時間で音を整えたい者”のために生まれました。
- 自宅で作曲し、そのままリリースしたいシンガーソングライター
- DTMでクラブミュージックを作るトラックメイカー
- ボカロ、劇伴、ゲーム音楽など、さまざまなジャンルに挑戦する個人クリエイター
これらのすべての者にとって、このプラグインは「即戦力の整音ツール」となりましょう。
ジャンルを問わず、特別な知識がなくとも使える――それがこの道具の最大の強みです。
ただし、素材(=ミックス)が整っていることが前提。
それを忘れず、音の仕上げを行えば、あなたの楽曲は、間違いなく“聴かれる作品”へと昇華するでしょう……
他のマスタリングツールとの違いと併用ポイント
bx_masterdesk True Peakは、「時短」「安全」「直感操作」の三拍子を備えたツール。
それゆえに、WavesやiZotope、FabFilterなどの精密系プラグインとは立ち位置が異なります。
精密なコントロールを求めるなら、他のツールと併用してもよいでしょう。
しかし、「音の流れを邪魔せずに整える」――そうした目的には、これひとつで充分な場合も多いのです。
また、StreamlinerやListenHubなどと組み合わせることで、配信時の音響も事前に確認でき、
最終的な“作品の完成度”をさらに高めることができましょう……
まさにこれは、“即戦力でありながら、学びのステージでもある”不思議なツールなのです……
考える前に、まず“聴く”こと
ふふふ……長き旅の最後にお伝えしたいこと――
それは、「考える前に、まず“聴く”こと」でございます。
まずはあなたの楽曲に使ってみて、Volumeを回し、Foundationを傾け、Tone Stackを触れてみるのです……
“耳が何を感じたか”
“何を心地よく思ったか”
その直感こそが、音を磨く者にとっての最大の武器です。
そして、使うたびにあなたの耳は育ち、
やがて、この魔法具の力を超えた先の領域へと踏み出すこともできるでしょう……
ふふふ……これで、あなたの旅はひとつの円環を結びました……
だが、終わりではありません――音の探求に終わりはないのですから……
どうかこの知識と体験が、あなたの音楽人生をより豊かに、そして自由なものへと導いてくれますように……
またいつでも、この音の結界に戻ってきてくださいませ……
次なる魔具があなたを待っておりますよ……🌙✨

はい、読みにくい〜!!
文末に「……」が多すぎる。占い師の雰囲気はでているが。。。
“導き”とか”魔具”みたいな、占い師風?の比喩が意外といい感じ。この口調に引っ張られて、読むのがスローになってしまうのが不思議。
今宵、この神秘の道具の力と仕組みをひも解いてみました…..
ふふふ……魔具「49鍵キーボード」を買っちゃった。MIDIキーボード沼に導かれる…..
ABOUT
-
"コとネ"と言います。本業はドラマーで、サポートやレコーディング、講師をやっています。
ドラマーだけどDTMerで作曲します。ソフトウェアをいじくり回すのが好きで、セール情報をウォッチするのも楽しい。ブログではDTMの疑問や悩みをメモしています。
Youtube(楽曲用)
Youtube(DTM用)
\ 制作のご依頼はこちら /