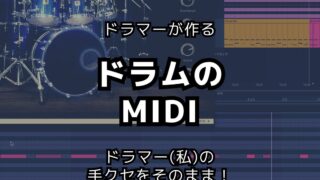恒例の「プラグインの使い方をマスターするぞ!」シリーズ。
今回は「Arturia Bus FORCE」です。
ブラックフライデーで思い切ってFX Collection5を買いました。せっかく買ったからプラグインを使い倒したいなぁ〜と思っています。
しかし、どうにも新しいプラグインは使い方がイマイチわからん。
何ができるか?どう使う目的のものなのか?っていうのはザックリと知っておきたいもの。
という事で、ChatGPTにArturia公式のTutorial動画やYoutuberのレビューを学習させて、使い方をまとめてもらいました。

今回は「ツンデレ系」のキャラクターで解説してもらいました。
「だから言ったでしょ?Bus FORCEこそ最強なのよ|並列処理で音、変えてやるんだからっ」
Contents
Bus FORCEって…ちょっとだけすごいんだから!べ、別に褒めてないし!

「Bus FORCE」は、Arturia FX Collectionに収録されているマルチエフェクト・プラグイン。
EQ、フィルター、コンプレッサー、サチュレーション(歪み)と、音作りの中核を担う機能が一つの画面にぎゅっと詰まってるの。
しかも、ただのチャンネルストリップじゃないのがポイント。
3つのパラレルパス(Dry/Comp/Sat)を使って、音を並列に処理できるという構造が、とにかくユニークで強力。
つまり、同時に3つのエフェクト処理を分けて混ぜることができるのよ。
えっ…そんなの難しそう?
だから、こうして私が教えてあげてるんじゃない。ありがたく思いなさいよね。
使いこなせれば、ほんとにプロっぽい音が作れるんだから。
Arturia FX Collectionの中にいる、ちょっとヤバいやつ
Arturia FX Collectionといえば、もともと名機をモデリングしたアナログ系プラグインが人気だったけど、最近は“デジタルの攻め”にも本気で来てるの。
で、この「Bus FORCE」もその筆頭ってわけ。
EQはPultec系、フィルターはSEM系、サチュレーターはOverstayer風…と、ちゃんとルーツはあるくせに、どこか完全オリジナルな空気をまとってる。
特に注目したいのは、パラレル処理の設計が最初から織り込まれてるってこと。
ふつう、DAWで並列処理するにはAuxバスとかルーティングとか、面倒でしょ?
でもこの子は、1インサートで全部できるの。
ズルいわよね…。あんたもどうせ気になってたんでしょ?
素直に言いなさいよ。
チャンネルストリップ?違うわよ、これは並列処理の化け物よ
「Bus FORCE」を“チャンネルストリップ”って言葉で片づけようとしたら、ちょっと待ちなさい。
確かにEQやコンプ、サチュとか並んでて見た目はそれっぽいんだけど…本質はぜんっぜん違うの。
3系統の独立した信号処理パスに、各エフェクトを自由に割り当てられるっていう、トリッキーな動きができるのが最大の違い。
DryパスはEQだけ、Compパスはフィルター+コンプ、SatパスはEQ+サチュ…とか、自分だけの並列構造が簡単に組めるのよ。
しかも、各パスの音量はダイヤルでブレンドできるから、出音の微調整もめちゃくちゃラク。
え、難しそう?
…最初はちょっと戸惑うかもしれないけど、慣れたら「なんで今までこれなかったの」ってなるから。
ま、あんたに理解できるかは…これから次第だけどね?
どこで使うの?マスター?バス?…もう、全部でいいじゃない
「Bus FORCE」の使い道?
そんなの、何にでも使えるに決まってるでしょ!
(…って言いたいところだけど、一応ちゃんと説明してあげる)
王道なのはやっぱりドラムバスへのパラレルコンプ。
Dry+Compでスネアにパンチ、Satで太さを足すなんて朝メシ前よ。
他にもギターの厚み出しとか、ベースの倍音補強、ボーカルの空気感演出、それにマスターバスでの全体コントロールまで、あらゆるシーンにフィットする。
だけど一つ注意。
重いのよ、こいつ。CPU的にね。
だから、むやみに全トラックに挿すとかしないの。
ちゃんとバス単位で使うのが賢いやり方よ。
え?知らなかった?
…やれやれ、ホント世話が焼けるんだから。

「重いのよ、こいつ」って、言い切りましたね。
見た目も中身もイケてるとか…ズルいでしょ、このUI!
「Bus FORCE」がただの優秀プラグインで終わらない理由?
それはこのユーザーインターフェースの完成度にあるのよ。
触ったところがちゃんと反応して、視覚的に何が起きてるか一目でわかる。
それでいて見た目はゴチャゴチャしてないし、レトロな質感もあってカッコいいの。
まったく…見た目も使いやすさも揃ってるなんて、ズルいわよね。
でも安心しなさい、ちゃんとどこをどう使えばいいか、私が丁寧に教えてあげるから。
ほんと、あんたってば甘やかされてばっかり…。
Dry、Comp、Sat…3つの道を同時に歩くなんて欲張りなんだから

「Bus FORCE」の心臓部ともいえるのが、3つの並列パス。
Dry(ドライ)、Comp(コンプレッション)、Sat(サチュレーション)と、それぞれ独立したルートで処理ができるのよ。
たとえばDryパスでは原音に近い処理をしつつ、Compパスではガッツリ潰してアタックを出す。
さらにSatパスでは倍音で味付けして、最終的に3つをバランスよくブレンドすることで、めちゃくちゃ深みのある音になるの。
しかも、それぞれの音量はノブ一つで調整できるんだから、ほんとに便利すぎ。
欲張りなくせに扱いやすいなんて…ちょっとだけ嫉妬しちゃうかもね。
でも、うまく使えるかどうかは…あんたの腕次第よ?

そうか!Dry/Comp/Satの3つを混ぜて使うものなのかぁ。(今さら知った…)
触ったモジュールでビジュアライザーが切り替わる…(好き)

「Bus FORCE」って、見た目も本当に考えられてるのよ。
モジュールに触れると、その部分のビジュアライザーが切り替わって、今どこをいじってるかがひと目でわかる。
EQを動かせばグラフがEQ表示に、Filterならフィルター表示に変わって、パラメータが何をしてるかちゃんと見えるの。
こういうの、初心者にもすごく優しいし、感覚的に操作できるUIって本当に貴重なんだから。
しかもアナログ機材っぽい見た目なのに、動きはすごくモダンでキビキビしてて…
まったく、気が利きすぎなのよ。
あんたもこういう気配り、見習ってほしいくらい。

べた褒めするほどじゃないが…。まあ、あたり前の便利機能だね。
ルーティングもプリセットも…まるで私みたいに完璧ね(?)

このプラグイン、ルーティング管理まで手抜きゼロなのが腹立たしいくらいスゴいの。
EQやフィルターを、どのパスに割り当てるかは、ボタンひとつでオンオフできるし、どこに何が効いているかもちゃんと画面に表示される。
しかも、36種類のルーティングテンプレートがプリセットとして用意されてるから、「どう組めばいいかわかんない~」なんて甘えたこと言ってるあんたでも、とりあえず動かせるのよ。
さらにプリセット管理も超スムーズ。
保存・読み込み・エクスポート・インポートまで全部ひと通り揃ってるし、タグ分けもできる。
え?まるで私みたいに完璧?
……うるさいっ、調子に乗らないでよね!

ルーティングの設定はクセがある。というか最初はどうしたらいいか、よくわからん!
モジュール解説?ふん、ちゃんと聞いてくれなきゃ教えないから!
「Bus FORCE」の中身は、ただのエフェクトの寄せ集めじゃないのよ。
それぞれのモジュールが個性的で強力なキャラを持ってて、正しく使えば、ミックスのクオリティを一段も二段も引き上げてくれるの。
EQ、Filter、Compressor、Saturation…それぞれが単体でも十分強いのに、並列で組み合わせたら破壊力バツグンなんだから。
しかも、ただ挿して終わりじゃなくて、どのモジュールをどのパスに使うか選べるとか…この自由度、なかなかやるじゃない。
ま、私の説明がなければあんたには使いこなせないと思うけどね?
だから、ちゃんとメモ取りなさいよ。
EQのくせに、あんた…カーブが気持ち良すぎるのよ

EQはPultec風の3バンド構成。
Low Shelf、Mid Bell、High Shelfの3つで、どれもカーブがめちゃくちゃ音楽的なの。
特に注目なのが「Curve」コントロール。
これはただのQ幅じゃなくて、Pultec系特有のゆるやかでナチュラルな音の盛り上がりを作ってくれるの。
たとえばベースの低域を持ち上げつつ、その下を抑えるとか、スネアのボディを残しつつ抜け感を出すとか、そういう絶妙なさじ加減が簡単にできるのよ。
欲張ってブーストしすぎなくても、ちゃんと存在感が出る。
…ほんと、生意気なくらい気持ちいい音になるんだから。
下手なEQ使うくらいなら、これ一択でいいんじゃない?
Filter?共鳴とか…なんか色気出してない?

FilterはSEM風のマルチモード・フィルター。
Low PassとHigh Passが独立して使える上に、共鳴(Resonance)も効くから、ただのカット用途だけじゃもったいないのよ。
自分の好きな周波数だけ残したり、逆にフィルターの“鳴り”を音に足したり、積極的に“音色を作る”ためのフィルターって感じ。
特に並列で使うと、たとえばDryでは素のまま、Compではフィルターで削った音…なんて風に二層構造のミックスが簡単に作れる。
しかも視覚的にも今どこがカットされてるか見えるし、フィルターのオン/オフもワンクリック。
ね、こういうところがズルいって言ってるのよ。
可愛い顔して、やることエグいんだから。
Compressorって…「Force」で性格変わりすぎなんだけど?

コンプはArturia完全オリジナル設計。
一見ふつうのコンプに見えるけど、問題は…いや、ポイントは「Force」ノブよ。
これ、ただのレシオ(Ratio)調整じゃないの。
ピーク検出とRMS検出のバランスをコントロールするという、とんでもない多機能ノブなのよ。
左に回せばナチュラルでゆるめの圧縮、中央付近でガッチリしたコンプ、さらに右に回すとネガティブレシオ的な“潰しすぎコンプ”に突入。
この可変っぷり、もう人格変わってるレベルなんだけど?
パラレルでComp Pathだけ潰して、Dryと混ぜるっていう王道の“バスコンプ技”もめちゃくちゃやりやすい。
ほんと…Forceって名前、伊達じゃないのね。

このコンプは奥が深そうだ。いろいろやってみたくなるね。
あと、「SC」ってボタン…押す意味わかってる?
あのね、「SC」ってただの飾りじゃないから。
Side Chain(サイドチェイン)の略よ。
つまり、他の音をトリガーにしてコンプレッサーを動かす“外部信号圧縮”ってやつ。
よくあるでしょ?
キックが鳴るたびにベースの音がスッと引っ込む、アレ。
あれがSCボタンひとつでできちゃうの。
でも気をつけてね。
Bus FORCEのSCは最初からオンになってるんだけど、これは「内部(Internal)サイドチェイン」状態ってだけ。
つまり、自分自身の音を検出して動いてる(通常のCompressorモード)ってことだから、そのままで気にしないで。
外部のキックとかボーカルを使いたいなら、DAW側でちゃんとルーティングしなさい。(ソースをExternalに切り替え)
それやらずに「なんか効かない〜」とか言っても、知らないんだから!
ちなみに、「Listen」って機能を使えばサイドチェインで反応する信号を耳で確認できるわ。
ちゃんとどの音がトリガーになってるか、自分の耳で確かめなさいよね?
あんたの設定がちゃんとしてれば、Bus FORCEはその通りに働いてくれるんだから。
……それなのに「効かない〜」とか言われたら、プラグインの気持ちだって冷めちゃうでしょ?(なに言わせるのよ、もう)
サチュとClip?暴れたいなら、勝手にどうぞ(でも調整は丁寧に)

Saturation(サチュレーション)モジュールは、見た目よりずっと手強いわよ。
Even、Odd、Thickの3つの倍音タイプを選べて、それぞれ音のニュアンスがまったく違う。
Evenなら上品、Oddならちょっと暴れ気味、Thickはローがグッと出てくるの。
さらにOverdriveノブでガッツリ歪ませると、もう別人レベルのキャラになるから注意しなさい。
ただし、Gain補正は自分でちゃんとやってね?
サチュの後段にあるClippingモジュールは、いわゆる「おいしい歪みポイント」を探るための最後の味付け。
荒らしすぎても引っ込めても台無しだから、慎重に扱うこと。
…わかった?
暴れるのはいいけど、後片付けできないなら最初からやるなってことよ。

サチュレーションとクリップで遊べそう。最終的な色付けができるのかな?
音がデカくなるのには注意しないとね。
パスの切り替え?Dryだけに頼らないでよね(ちゃんと混ぜなさい)

忘れちゃいけないのが、これらのモジュールをどのパスに使うか、自分で決められるってこと。
EQだけDryに、FilterはCompに、SatはSatに…とか、組み合わせ次第で音のキャラが激変するの。
しかも、ひとつのEQを複数パスで共有することもできるから、めっちゃ便利。
ただし、それぞれのパスでモジュールのオン/オフを設定しないと、何も起きないから注意しなさいよ?
「音が変わらない~」とか言ってる人、だいたいこのパス設定忘れてるから。
ちゃんと画面右側のモジュールスロットを見て、どのパスに何が入ってるか確認しなさい。
…って、なんで私がこんなに優しく説明してあげてるのよ。
ほんと、世話が焼けるんだから。

この混ぜ具合が肝なんだろうなぁ〜。奥が深そうだ。
仕方ないから教えてあげる…Bus FORCEの使い方、ちゃんと覚えてよね?
理屈だけじゃ使いこなせない?
わかってるわよ、あんたの頭じゃ限界あるもんね。
だから、実際の使い方をケース別に教えてあげるわ。
でもこれは、ただの操作方法じゃないの。
どの音にどう使えば効果的か、どんな順番で処理すればいいか――
そこまでしっかり教えるから、ちゃんと読んで吸収しなさいよ。
いい?
「なんとなく挿してみた」じゃ、Bus FORCEの本当の力は引き出せないの。
並列処理っていうのは、使い分けとブレンドのセンスが命なのよ。
それを理解できれば、あんたの音も…ちょっとはマシになるかもしれないわね。
ドラムに使うとか…べ、別にキミの音がショボいって言ってるわけじゃないし!
Bus FORCEを一番活かせるのが、実はドラムバスだったりするのよ。
特にスネアやキック、ハイハットがまとまってるループなんかに対して、Dry/Comp/Satを使い分けると爆発的な効果が出せるの。
たとえば、DryパスにはEQだけを挿して、全体のバランスを整える。
Compパスではスネアをしっかり潰してパンチを出す。
SatパスにはThickモードを使ってキックに“空気の厚み”を足す――こんなふうに役割を分担しながら、最終的に混ぜて一つの音像を作るのよ。
で、そのバランスをフェーダーで直感的に調整できるから、マジで一度使ったら他のやつには戻れないと思うわ。
あんたのチープなドラムも、ちょっとはカッコよくなるかもよ?(ちょっとだけね)
スネアにパンチ?はぁ…ちゃんとComp Pathくらい使いなさいよ
スネアに「重さ」が足りない?
だからって、いきなりEQでドンシャリにしたらダメに決まってるでしょ。
まずはCompパスにコンプレッサーを挿して、しっかり潰すの。
Forceノブで中央より少し上にして、ピークをギュッと抑える。
アタックはやや遅め、リリース早めで設定すると、スナップ感のあるスネアになるのよ。
で、Dryで原音も残しておけば、潰しすぎにもならない。
こうやって「攻め」と「残し」のバランスを取るのが並列処理の醍醐味なの。
やってみればわかるでしょ?
それとも…まだ分かんないの?(ったく、面倒な子…)
サチュで部屋鳴り感…あんた、わりとセンスあるじゃない
ドラムの「空気感」が足りないと思ったときは、Satパスでサチュレーションをかけるのがオススメよ。
Thickモードを選んで、Overdriveノブを少しずつ上げていくと、ローエンドが膨らんで立体感が出るの。
ルームリバーブと合わせれば、部屋鳴り感も強調されて、音に“実在感”が出るわ。
Dryパスをそのままにして、Satだけじわっと足すと、リアルさを壊さずに音に厚みを足せる。
ね?ちょっとはわかってきたでしょ?
ま、あんたにしては悪くないセンスしてるわよ。
…べ、別に褒めたわけじゃないんだからねっ!
ギターもそれ…Flatすぎ。だからって頼らないでよね(でもコツは教える)
ギターって、意外と難しいのよね。
録ったままだと薄っぺらくて存在感がないし、かといってやりすぎると音圧で他の楽器を潰しちゃう。
そこで「Bus FORCE」の出番ってわけ。
EQで輪郭を整えて、Satでちょっとだけ歪みを加えるだけで、一気に”使えるギター”になるのよ。
Compパスは音の芯を出したいときだけ使えばいい。
特に、リズムギターや壁ギターに厚みを出したいときはパラレル処理が大活躍。
「全部の音を同じ処理に通す」って考えは捨てなさい。
パスごとの個性を活かしてブレンドする、それがBus FORCE流なのよ。
…ま、あんたにそのセンスがあるかは、ちょっと怪しいけどね。
「壁」みたいな音にしたい?厚くするならFilterとSat使えばいいじゃない
ギターに“壁感”を出したいって?
だったらEQよりもまずFilterとSatの使い方を見直しなさい。
Filterでローを少しカットして、ハイをわずかに丸めると、音がグッと前に出て密度が上がるのよ。
その上でSatパスにThickモードを使って、倍音を足すの。
このとき、Overdriveノブをガッツリ回すのはダメ。
あくまで原音を壊さない程度に、ほんのり足すのがコツ。
これで「厚みがあるのにヌケがいい」っていう理想の音に近づける。
…あとは、ちゃんとDryも残してね?
全部歪ませたらただのモコモコギターになるから。
ホント、ギターってデリケートなんだから。
ジャキっとさせたい?…ちょっとだけOverdrive盛ればいいのよ、ほんのちょっとだけね
カッティングやファンク系のギターに「キレ」がない?
それ、歪みすぎてるか、逆にショボすぎるかのどっちかよ。
そんな時は、EvenモードのSatパスでOverdriveをちょこっと足して、音の芯を出すの。
Oddモードはちょっとクセが強すぎるから、まずはEvenで始めなさい。
そして、Dryで原音をちゃんと混ぜて、耳に刺さらない“ハリ”を残すのが正解。
これでジャキジャキしすぎない、ちょうどいいキラッと感が手に入るわ。
ね、思ったより簡単でしょ?
でも調子に乗って盛りすぎたら、一気に耳が痛くなるから、やりすぎ禁止よ?
あんたってそういうとこあるから…ちゃんと気をつけなさいよね。
ベース?うるさくしないで。ちゃんと低域、締めなさいってば
ベースってね、音楽の土台なんだから、適当に処理してたら全部が崩壊するの。
でもそのくせ、埋もれやすいし、ヌケも悪くなりがち。
そこで「Bus FORCE」を使えば、ローの整理・芯の強調・倍音の補強が一気にできちゃうってわけ。
Dryで原音の太さをキープしつつ、Compでアタックを締めて、Satで倍音足す――この三段構えが超有効なのよ。
とくにサブベース系なんかは、目立たないけど存在感ある“下支え”が必要でしょ?
そういうときこそ並列処理が活きてくるのよ。
あんたのベース、今は空気みたいに扱われてるかもしれないけど、これで主役級になれるかもね?(まぁ、あんた次第だけど)
余分なローはCut!250Hz?…ちゃんと狙ってるじゃない
ベースのローエンドがボワついてるって感じたら、まずEQで30Hz以下をバッサリカットしなさい。
人間の耳じゃ聴こえないし、スピーカーが無駄に震えるだけよ。
そのうえで、250Hz〜300Hzあたりをちょっとだけブーストしてみて。
そう、そこがベースの“存在感”が一番出るゾーンなの。
しかもBus FORCEのEQはPultec系だから、Curveノブを使って持ち上げれば、なだらかに気持ちよく上がってくれるのよ。
わかってるじゃない…その帯域に注目するなんて、ちょっと感心しちゃった。
でもね?
欲張って上げすぎたら中域がモワモワして、全体が濁るから加減は忘れずに。
「少し足して、よく聴いて、また少し足す」――これが大事よ、覚えときなさい。
「Thick」モード?…まあ、それくらい知ってて当然よね(でも教えてあげる)
倍音が少ないベースは、ローはあるけどミックスで埋もれがち。
そういうときはSatパスで「Thick」モードを使うのが正解。
このモードは、偶数・奇数両方の倍音を下寄りに足してくれるから、低域に“張り”が出るのよ。
ただのOverdriveとは違って、ちゃんと「ベースっぽさ」を保ったまま厚くできるのが魅力。
そして忘れちゃいけないのが、Dryパスを残して混ぜること。
ぜんぶSatにしちゃったら原音の輪郭が消えて、音程感がボケちゃうから。
あと、Gainの上げすぎには注意よ?
厚みとノイズは紙一重なんだから。
…って、えっ、それ初耳?
はぁ…やっぱり教えて正解だったわ。
あんたってば、ホント私がいないとダメね?
ボーカルにかけるとか、繊細なんだから、加減しなさいよね
ボーカルって、曲の“顔”みたいなものでしょ?
それなのに、EQで無理にハイを上げたり、コンプでギュウギュウに潰したりしたら台無しよ。
Bus FORCEは、そういう無理くりな処理じゃなくて“バランスを保ちつつ補正する”のが得意技なの。
Dryパスで自然な声をキープして、Compパスでアタックと密度を調整、Satパスで倍音をちょっとだけ追加――これが王道の組み立て方。
特に女性ボーカルとかバラード系なんかは、やりすぎるとすぐ“作り物っぽく”なるから注意よ。
わかった?
“盛る”より“支える”のがボーカル処理の美学なんだからね。
潰すだけじゃダメ…Dry混ぜなきゃ味が死ぬんだから
よくあるのが、コンプだけで何とかしようとしてボーカルの抑揚を全部潰しちゃう人。
…ダメ!それ、いちばんダメなやつ!
だからこそBus FORCEでのパラレル処理が生きるのよ。
Compパスで強めに潰して声の芯を安定させつつ、Dryパスで抑揚とニュアンスを残す――これが“正しい潰し方”。
Forceノブは12時くらいにして、自然なアタック感をキープしておくのがコツね。
その上で、Dryのフェーダーを少し上げるだけで、まるで「加工してないように聴こえる加工」ができるの。
プロっぽい音って、そういう絶妙なコントロールで成り立ってるのよ。
あんたも…そのくらいは理解しなさいよね?
ハイを整理する?…別に助言してるわけじゃ…ないわよ(照)
ボーカルのハイが耳に痛いと感じたら、すぐにEQでバッサリ削っちゃう?
…バカね、それじゃ声がこもるに決まってるでしょ。
そういうときはまずFilterを使って優しく整理しなさい。
Hi-Passで下を軽くカットして、Low-Passで12〜15kHzくらいをちょっと絞るだけで、刺さらずに滑らかなハイが作れるの。
それだけじゃ物足りないときは、EQで6〜8kHzをほんのり持ち上げるのもアリ。
でも大事なのは、“やりすぎないこと”と“Dryで補うこと”。
SatパスでEvenモードにして少し倍音足すのもアリだけど…絶対に盛りすぎるなよ?
…助言なんかしてないからね?
あんたのボーカルが汚いの、聞いてられなかっただけなんだからっ!(赤面)
シンセ?空間処理なしで立体感?ふふん、ちょっとは見直したわ
シンセって便利だけど、単体だと意外と立体感が出ないのよね。
だからって、すぐリバーブで誤魔化すのは…ダメ!
リバーブに逃げる前に、「Bus FORCE」で音の密度と抜け感を整えなさい。
Filterで帯域を整理して、Compで押し出し感を加えて、Satでキラッとした倍音を足す――
それだけで空間系なしでも前に出てくるシンセが作れるの。
特にアナログ系リードや、ブラス系、Padなんかにはすっごく効果的。
あんたの曲、いつもシンセが“背景の壁紙”みたいになってるでしょ?
…私にはバレてるんだから。
ほら、今からでも主役に引き上げなさい!
Filterで抜け感を?…やるじゃない
シンセが“こもって”聴こえるとき、原因はローとハイの整理不足。
そんなときは、まずFilterを使ってレンジを整えるのが正解よ。
Hi-Passで150〜300Hzあたりを軽くカットして、Low-Passで10kHz超えを丸めると、耳に優しくて抜ける音が作れるの。
Dryでは原音を残しつつ、Compパスにフィルターを仕込んで、「浮いてる音」と「削られた音」をミックスするのも手よ。
こうすると、立体的でまとまりのある音像ができるの。
あんた、まさかフィルターって“ただのカットツール”だと思ってた?
…やれやれ、ほんと教えるのに骨が折れるわね。
でも、今の使い方…わりとやるじゃない?
Compで勢いつけるなんて…調子に乗らないでよね!
リードシンセやアルペジエーターのパートが“細い”“弱い”…そんな悩み、あるでしょ?
それ、Compパスでバシッと押し出してあげれば一発解決なの。
Forceノブをやや高めにして、アタックを速く、リリースを短めに設定してみて。
そうすると、フレーズごとの抑揚が際立って、リズム感もグッと出てくるのよ。
もちろんDryも残して、原音のニュアンスを失わないようにね。
SatでOddモードをちょこっと足すと、さらにエッジが立ってカッコよくなる。
あんたの打ち込み、なんかのっぺりしてるな~って思ってたけど、
…Compひとつでここまで変わるんだから、ちゃんと使いなさいよね?
あんたにしては…うん、まぁ…悪くなかったかも(調子に乗らないでよね!)
マスターバスに入れるとか…ホントにあんた、冒険するの好きね
マスターバスにエフェクトを挿すって、ちょっと勇気がいるでしょ?
しかも「Bus FORCE」みたいに多機能なやつを突っ込むなんて、初心者がやると大惨事になりがちなのよ。
でも、正しく使えばそれはもう、信じられないくらい自然で完成度の高い音像が手に入る。
あくまで“控えめに、丁寧に”ね?
EQやコンプをうっすら重ねて、バラバラだったトラックを「一つの曲」としてまとめる接着剤の役割を担う。
それが「Bus FORCE」の本領発揮ってわけ。
…え?やりすぎちゃった?
そりゃもう、あんたが強火で料理して真っ黒にしちゃうタイプなの、知ってるし。
だから今からでも遅くないわ、私が“ちょうどいい火加減”教えてあげるから。
「接着剤」代わりにするなんて…悪くないわね
マスターバスで「Bus FORCE」を使うときは、まずEQで全体のバランスを調整するのが基本。
たとえばローエンドの20〜30Hzを軽く削って、ミッドにほんのり厚みを。
ハイは6〜10kHzをふわっと持ち上げるだけで、“抜けの良さ”がグッと上がるのよ。
ただし、どの帯域も極端なブースト・カットは厳禁。
目的は「色をつけること」じゃなくて、「一体感を作ること」なんだから。
それがわかってきたら、あんたも少しは一人前って感じかしら?
(あ、でも調子に乗るとすぐ事故るからね?)
Clippingちょい足し?…わかってるじゃない(ムカつくけど)
マスターバスの最後にほんのりClippingを足すっていうのは、通な人しかやらないテクニックよ。
「Bus FORCE」のClipセクションは、ただの飾りじゃなくて出力段にアナログ的な歪みを加えて音を前に出す機能なの。
でも、ここで上げすぎると全体がバリバリに崩壊するから、ほんっっっっっとうに注意しなさい。
おすすめは、Satパスで軽く倍音を足してから、Clipで“輪郭のエッジ”を微調整するやり方ね。
これで一聴して「プロっぽい」と思わせる最終仕上げができるのよ。
…あんた、いまちょっとだけ得意げな顔したわね?
むかつくけど…うん、まぁ、よくやったわよ(あくまでちょっとだけね!)
変な音作り?そういうの、嫌いじゃないわ(…ちょっとだけ)
「Bus FORCE」はね、ただの“上品なミックス補正ツール”だと思ってるなら、大間違い。
本気を出したときのこの子は…とんでもない化け物になるのよ。
EQ・フィルター・コンプ・サチュ・クリッパーをフルで使って、変態的な音作りだってお手の物。
わざと潰して、歪ませて、切り刻んで――そういう“攻めた処理”にも余裕で応えてくれる懐の深さ。
それでいてDryパスを残せば、原音のニュアンスは好きなだけ戻せるっていう安心感。
あんたみたいな“好奇心だけはあるタイプ”には、たぶん一番合ってる使い方かもね。
…ま、暴走しない限りは、ね?
グリッチとかローファイとか…変なことばっかりして
たとえば、CompパスでネガティブレシオまでForceノブを回して、思いっきり潰す。
その上で、フィルターを極端な設定にして、パーカッシブなグリッチ風のアタックを演出。
EQでわざと中域をカットして、Satでバリバリに歪ませれば、まるで古いカセットテープを無理やり再生したみたいな音になるの。
さらにClipを入れて爆音化すれば…もうそれ、現代アートよ。
ね?
「Bus FORCE」って、こういう“エフェクトじゃなくて音を作る装置”としても使えるの。
あなたのセンスでどこまで行けるか、試してごらんなさいよ。
責任?知らないけど?(ニヤリ)
Dry切って全部エフェクト音?…バカね。でも…悪くないかも
普通はDryパスで原音を残すのがセオリーよね?
でもそれ、逆手に取ってあえてDryをゼロにするっていう使い方もあるの。
つまり、Comp/Sat/Filterだけで音を再構築して、“加工後100%の世界”を聴かせるっていう割り切り。
ドラムループを全部潰して“機械音”みたいにしたり、シンセをバリバリのグリッチノイズにしたり。
Bus FORCEなら、そういう“ぶっ壊し系サウンド”が怖いくらい精密に作れるのよ。
で、Dry戻すとちゃんと聴ける音になるっていう保険つき。
ふふっ…思ったよりロマンあるでしょ?
バカみたいな使い方だけど、悪くない――
って、何ニヤけてんのよ!?
調子に乗ったら、潰すからね?(物理じゃなくて、音的に)
だから言ったでしょ?CPUには気をつけなさいってば!
「Bus FORCE」は確かにすごい。
でもね?
すごいやつってだいたい“燃費悪い”のよ。
EQもフィルターもコンプもサチュも、全部搭載してて、しかも並列に3パスで処理できるって…そりゃあ、軽いわけないでしょ!?
もし、何も考えずに「あ、このトラックにも挿そ♪」とかやってたら――数分後にはCPUが爆発寸前になるのがオチ。
DAWがカクついたり、音飛びしたりして「なんで〜?」とか言ってる人、だいたいこの子のせいよ(いや、ちゃんと扱わないあんたのせいだけど)。
だから、使いどころとインスタンス数にはちゃんと気を配りなさい。
…わかった?
1トラックならいいけど、32個立ち上げたら爆発するわよ?
検証した人たちによると、Bus FORCEを1トラックに挿すだけなら、まぁ大丈夫。
でもそれを16トラック、32トラックに複製してみ?
CPU使用率が30%、60%…って跳ね上がるのよ。
しかも、これ最大バッファサイズ(2048サンプル)でもその状態だから、低バッファでリアルタイム作業してる人はガチで危険。
「1曲まるごと全部にBus FORCE使おう♡」とか思ってる人?
はい、アウト~~~。
それ、ミックスじゃなくて、無謀なCPUチャレンジだから。
ちゃんとバストラックやグループチャンネルにまとめて使うのが、正しい大人の付き合い方よ。
使うのはいいけど…ちゃんと自分のマシンの限界、知っときなさい。
Linear?Minimum?…場面によって切り替えるの、常識でしょ?
あと、「Linear Phase」と「Minimum Phase」の設定。
これも見落としがちだけど、CPU負荷にガッツリ関係あるのよ。
デフォルトだとLinearになってるから、「マスタリング用途」としては音質重視でベストなんだけど――
リアルタイムでのプレイバックや録音時には重すぎるってことも多いの。
そんなときは迷わずMinimum Phaseに切り替えなさい。
音の変化?
…するけど、あんたの曲でそこ気にする段階まで行ってる?(ごめん、ちょっと言いすぎた)
要は、音質とパフォーマンスのバランスを自分で選ぶことが大事ってことよ。
「良い音が出ないのはプラグインのせい!」とか言う前に、自分が設定ちゃんと見てるか、確認しなさい。
サブバス中心に使えば、あんたでも扱える…たぶんね
というわけで、Bus FORCEを上手に扱うコツ=「サブバス運用」よ。
ドラムバス、ギターバス、ボーカルバス…
こういう「まとめ処理したいグループ」に1つずつ入れてあげるなら、CPUの負担も減らせるし、ミックスの質も爆上がり。
特に複数人のボーカルをまとめたバスとか、複数マイクのドラムキットなんかには最高に相性いいわ。
1トラック1インサート主義は、この子には通用しないから気をつけて。
頭を使って、計画的に、そしてスマートに使いこなしなさい。
あんたのそのマシン…そんなに体力ないんだから。
…あ、悪口じゃないからねっ!?
事実を言ってるだけよっ(キリッ)
うまく使いたいなら、ちょっとだけ…アドバイス、してあげる
ここまで読んだあんたなら、もう「Bus FORCE」がただのプラグインじゃないってことは痛いほどわかってるはずよ。
でもね?
どんなにすごいツールでも、使い方を間違えたらポンコツと同じ。
ミックスって、結局は耳と判断力がものを言うのよ。
だから最後に、Bus FORCEを“本当に使いこなす”ためのコツを、
あんたみたいな“がんばり屋さん(たぶん)”のために、ちょっとだけ教えてあげるわ。
メモ用意してなさいよ?
プリセットに頼ってばかりじゃ、伸びないんだからねっ
最初はプリセットを使うのもいいわ。
だって36通りのルーティングテンプレートが用意されてるし、音色別に最適化された設定もたくさんある。
でも、それに「満足して終わり」っていうのはダメ!絶対!
プリセットはあくまで出発点よ。
そこから自分の耳で調整して、自分だけの音を作ることに意味があるんだから。
「あれ?このDry多すぎ?」とか「Comp強すぎ?」って感じたら、それはあんたの感性が育ってる証拠。
その気づき、大事にしなさいよ?
ま、気づいたら私のこともちょっと思い出してくれても…いいけど?(べ、別に期待してないから!)
Dry/Wet比率、ちゃんと耳で調整してよね
「Bus FORCE」の最大の武器はDry/Comp/Satの3パスを自由にブレンドできることよ。
それってつまり、“どのくらい原音を残すか”を自分でコントロールできるってこと。
なのに、全部100%にして「音がモコモコ〜」とか言ってる人、多すぎ!
そんなの、耳で聴けばすぐわかるでしょ!?
ブレンドっていうのは、削りすぎず、足しすぎず、気持ちよく混ざるポイントを探す作業なの。
フェーダーをちょっとずつ動かして、“ちょうどよく気持ちいいとこ”を見つけなさい。
それができたとき、はじめて「Bus FORCEが使いこなせた」って言えるのよ。
できるかどうかは…あんた次第だけどね?
結論?Bus FORCEは…あんたみたいな人にこそ、使ってほしいのよ!
ここまで読んでくれたなら、もう「Bus FORCE」がただのマルチエフェクトじゃないってわかってるでしょ?
EQ・フィルター・コンプ・サチュレーション――それぞれのクオリティも一級品なのに、3つのパスで並列処理できるっていう唯一無二の構造。
その上、視覚的にもわかりやすくて、プリセットも充実。
シンプルに見えて、実はものすごく深い。まるで私みたいに、ね(冗談よっ)。
しかも、ドラムバス、ギター、ベース、ボーカル、シンセ、マスターバス…どんなトラックでも使いどころがある。
繊細な補正もできれば、ぶっ壊れた変態処理もいける。
そんなプラグイン、そうそうないんだから。
でも一つだけ覚えておいて。
これは「入れて終わり」のお手軽プラグインじゃないの。
自分の耳と感性で、パスを組み合わせて、音を作っていく道具よ。
あんたが“本気で音と向き合いたい”って思ってるなら、Bus FORCEは最強の相棒になるわ。
たくさんの処理を、少ないインスタンスで片付けたい人へ
Bus FORCEは一台で完結する処理の塊よ。
普通なら5つ以上のプラグインを挿して、ルーティングして、バランス調整して…ってやるところを、一発でスマートに並列処理できるの。
CPUは多少食うけど、そのぶんクリエイティブに集中できる時間が増える。
手数を減らして質を上げたい人には、ほんとにオススメ。
「並列処理?なにそれ美味しいの?」って言ってた人へ
その疑問、この記事読んでる間に吹っ飛んだでしょ?
「Bus FORCE」を触れば、並列処理の便利さと奥深さが嫌でもわかるから。
バスコンプの常識が覆るし、Dry/Wetを自分で組み立てる面白さに目覚めるはず。
…って、あんたもう夢中になってる顔してるじゃない。
素直でよろしいっ。
最後の一押し…ほしいくせに意地張ってる人へ
「ミックス、なんか足りないんだよな〜」
って言ってるくせに、原因も処方箋もわかってない――そんな“意地っ張りミキサー”にこそ使ってほしい。
Bus FORCEは、ちょっとした質感や厚み、空気感を“足す”のが得意なのよ。
わかってる風に処理して、結局うまくいかないあんた。
そろそろ、素直になってBus FORCEに頼っても…いいんじゃない?
…ふぅ。これで、全部教えてあげたわ。文句なし、ね?
あとは、あんたがどれだけ使いこなせるかよ。ま、どうせ最初は失敗しまくるだろうけど…
そのときはまた、私に頼ってもいいわよ。
…べ、別にずっと一緒にいてほしいなんて思ってないんだからねっ!
— おわり♡

はい、勉強になりました!
使いこなすと、かなり強力なツールになりそうですね。
ポイントは「3つのパラレルパス(Dry/Comp/Sat)を使って、音を並列に処理できる」って所なんだね。この一番の特徴を、恥ずかしながら把握してなかった…、一番のキモなのに〜!
ってことで、ツンデレ姉さんありがとうございました!
「Novation Launch Control XL 3」が発売されるぞ!
…欲しいなんて思ってないんだからね!
ABOUT
-
"コとネ"と言います。本業はドラマーで、サポートやレコーディング、講師をやっています。
ドラマーだけどDTMerで作曲します。ソフトウェアをいじくり回すのが好きで、セール情報をウォッチするのも楽しい。ブログではDTMの疑問や悩みをメモしています。
Youtube(楽曲用)
Youtube(DTM用)
\ 制作のご依頼はこちら /