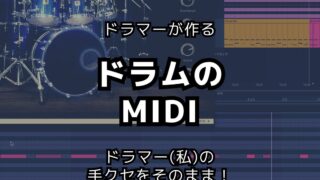なんだかんだ8年使っている「YAMAHA HS-7」。
良いところも・悪いところも、ホンネでレビューします!
DTMの作業で大切なモニタースピーカー。私は「YAMAHA HS-7」を愛用しています。
“愛用”と言いましたが、実際は「買ったから使い続けてる。新しいのを買う余裕ないし。」という理由が大きいですが、それでも8年間使い続けているのは、、、
「いいスピーカーで不満がない」
はい、まさにこれが一番大きな理由ですね。
そう、全く不満がありません。そのため買い替える必要もない。スピーカーってそんなに何度も買い替えられるものじゃないしね。
という事で、8年使った感想をメモしておきます!
Contents
YAMAHA HS-7とは?まずはどんなスピーカーなのかを簡単に紹介
YAMAHA HS-7は、同社のモニタースピーカーシリーズ「HSライン」の中間モデル。
5インチの「HS-5」と、8インチの「HS-8」のちょうどあいだに位置する6.5インチのウーファーを搭載し、「音のバランス」と「設置のしやすさ」の両立(中間のいいとこどり)を狙ったモデルって感じ。
『クセのない音質設計で、ボーカルや楽器の輪郭がはっきりわかりやすく、ミックス時の判断を助けてくれるのが特徴です。』(という評判をよく目にします。)
出力は合計95W(低域60W+高域35W)とパワフルで、6〜10畳程度の部屋なら余裕を持って鳴らしきれます。

というか、正直「でかい!」ですね。
設置するのもでかいし、音を鳴らすのも大きさを活かすには、ある程度Volumeを上げたほうがいいので、住宅環境を考慮する必要あり!
ただ、「HS-5じゃ物足りないけど、HS-8は大きすぎる」そんな人にとって、HS-7はちょうどいい落としどころだと思います。
満足する音質で、8インチほどバカでかくない。
制作の相棒として長く使える、安定感のある一台である事は間違いないっす。
HS-7の音質はどう?クセのない素直な鳴り方が魅力
HS-7のいちばんの魅力は、その「クセのなさ」でしょう!
よく「フラット」みたいな言い方がありますが、まさにそんな感じ。フラットの定義が曖昧ですが…、まあ「クセがない・味付けがない」って感じ?
そう、派手な演出も、気持ちよくなるような甘いチューニングもありません。
だからこそ、「素直な音でバランスを冷静に見つめることができる」と言えるかな。(かっこよく言うと)
高音の聞こえ方
高域はクリアでスッと伸びるけれど、鋭く刺さるような感じはありません。
シンバルやアコースティックギターの高音が、耳に痛くないのに細かく聴き取れる──そんな印象です。高音があまりカリカリしていないっていうのかな?だから、すこし高音が丸く感じる(解像度が低く感じる?)人もいるかもね。

高音があまりカリカリしている=解像度が高い…と勘違いしがちなので要注意。HS-7はカリカリしてないけど、ちゃんと高音が聞こえます。でも音が丸いから混ざって聞こえる(錯覚する?)こともあります。
中音の聞こえ方
中域はとくに得意な帯域で、ボーカルがはっきり出ます。ミックスで主役になるパートの調整がしやすいのは大きな利点。
とはいえ、私はあまりボーカル曲は作らないので、実はあまりよくわからん!!(でも、他のレビューではボーカルがよく聞こえるって話なので、たぶんそうなのでしょう。)

「スネアが鋭く聞こえる」というレビューも目にしますが、ドラマー的にはもうちょっと欲しいところ。でも、これはドラマーだからだと思う。
まあ、スネアのチューニング(音の質や高さ)によってもぜんぜん違うので、HS-7がハマる時もあれば、ハマらない時もある。そんな感じ。
低音の聞こえ方
一方で、低域はやや控えめです。
ズンズン響くタイプではなく、「必要なだけ鳴る」誠実なローエンドって感じ。
ヒップホップやEDMをがっつり作る人にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。
「サブウーファー(HS8S)との組み合わせを検討するのがベター」って口コミをよく目にするけど、「そりゃそうだろ、でもそうもいかんだろ!」って感じですよね。。。
だからといって「低音が見えない」って事は全くありません。むしろちゃんと見える。
ただ、物足りないというか「環境によってどう鳴るのか?」を想像するのに経験が必要になると思います。
ズーンと響く低音が足りなく感じるのは確か。そのため、必要以上に低音を効かせすぎて、リスニングのスピーカーで聞いた時に「低音デカ!!」みたいなミックスになっちゃう事がよくあります。
クセのない素直さが魅力…だが、その無難さが飽きる!?
低音も含めて、全体としては「原音の姿をそのまま映し出すような“素直な音”」だと思います。控えめに言って「これ買っておけば間違いない」系のアイテムです。
そのクセのない素直な音は、悪く言ってしまえば「THE 無難」。
そう無難なのよ。無難すぎるのよ!!
それがこのスピーカーの特徴で、一番の魅力ではあるんだけど、無難すぎると「うーん、もっとクセのある音で作曲したいな」と思ってしまうのも事実。
そうなんです、HS-7を8年使った今、むしろ逆に「ちょっとクセのある系のモニタースピーカーも欲しいな」とか思い始めてる。
とくに電子系のジャンルは、ちょっと派手さに欠けるので、作曲もテンション上がらないし、ミックスも微妙にリスニング時の音を想像しずらい。派手すぎるマスタリングになりがちっていうのかな?
スペックと価格のバランスは…コスパは悪くないんじゃないかな
YAMAHA HS-7は、1本あたりおよそ30,000円前後(ペアで約60,000円)の価格帯に位置するモニタースピーカーです。
スペック・性能・実際の音質を踏まえると、悪くない(というか全然いい)お値段だと思う。
長く使っても「飽き」が来にくく、結果的にコスパが高いと感じるタイプの製品です。
スペック面を見ていくと、ウーファーは6.5インチ、ツイーターは1インチのドーム型。
出力は合計95W(低域60W・高域35W)で、6〜10畳程度の部屋ならしっかり鳴らせるパワーを持っています。
周波数特性は43Hz〜30kHzと、低域も高域も広くカバーしています。
入力端子はXLRとTRS(いずれもモノラル)を搭載。
バランス接続対応なので、オーディオインターフェースとノイズレスに接続できます。
背面にはRoom Control(低域カット)とHigh Trim(高域調整)も備わっており、設置環境に合わせた音作りが可能です。
HS-5・HS-8との違いは?自分の制作環境に合うモデルの選び方
YAMAHAのHSシリーズは、ウーファーのサイズごとに「HS-5」「HS-7」「HS-8」という3つのモデルが用意されています。
どれも基本的な設計思想は共通ですが、部屋の広さや制作スタイルによって選び方が変わります。というか、物理的に・住宅環境的に大きさを選ぶしかない。
まずHS-5は、コンパクトで扱いやすく、デスクトップ環境に向いています。
中高域の再現力は優れていますが、低域はかなり控えめ。….というレビューを目にします。
確かにHS-7も低音がちょっと物足りなかった(見えないわけじゃない)ので、HS-5は低音の満足感はないかもね。(正直、わかりません。。。)
4〜6畳程度の部屋や、モニタースペースに制限がある人には向いていますが、バランスの取れたモニタリングを求めるなら物足りなさが出る場面も。
対してHS-8は、パワーとサイズ感が段違い。
8インチウーファーならではの低域再生力があり、EDMやシネマ系の音楽にも対応できる強さがあるという評判です。部屋の大きさを気にしなければHS-8買っとけ!っていう口コミをよく目にします。
ただし、サイズが大きく、設置場所や部屋の吸音環境によっては“鳴りすぎる”というか、一般家庭では厳しいよね?って感じ。
でかいスピーカー買って、小さい音でしか鳴らさない…っていうのもアレだし。。。
そして、HS-7。
5と8の“間”というだけでなく、実際にバランス感がとてもいいモデルです。HS-5/HS-8を買っていないので、推測ではあるけど、まじでバランス感は絶妙だと思う。
6.5インチのウーファーで、HS-5よりしっかり低域が出せて、HS-8ほど場所を取らない。
個人制作やホームスタジオにちょうどいい出力感と、クセのない音作りのしやすさがあります。
よくある後悔パターンの口コミとしては──
「HS-5を買ったけど、やっぱり低音が足りなかった」
「HS-8を勢いで買ったけど、設置場所が狭くて鳴らしきれない」
こうした失敗を避けたいなら、HS-7を基準に、部屋と目的に応じて調整するのが現実的だと思います。

とはいえ、それでもHS-7もデカいけどね。
まじで「どう置こうか?」と悪戦苦闘しました。
デカいから、自分の耳からある程度の距離は離したい。でも、離すと壁にピッタリくっついちゃうし、パソコンモニターも遠くに設置しなきゃいけなくなる。(音の反射を考えると、スピーカーよりもパソコンモニターを奥に置きたいよね。)
得意なジャンル、不得意なジャンル|HS-7が合う音楽・合わない音楽
HS-7は“クセのない音”をモニターできることが最大の武器ですが、その特性上、向いているジャンルとそうでないジャンルがはっきり分かれます。
基本的には何でもいい感じになってくれますが、ジャンルによって得手不得手があるなぁ…ってのはマジで感じます。
まず得意ジャンル。
アコースティックや弾き語り、ポップス、ロック、ジャズなど、音の輪郭・中域のバランスが重要な楽曲には非常に強いです。生楽器・生バンド系の音楽にはすごく良い!
「やっぱ、YAMAHAだなぁ」と感じますね。
サウンドトラックや劇伴みたいな、繊細な表現を求められるジャンルでも本領発揮しますね。
空間処理やステレオの広がりを冷静に見極めるには、このクセのなさが強みになります。(でも、リバーブがよく見えるか?というと…普通って印象。)
一方で不得意なジャンルもあります。
EDMやヒップホップなど、「低音が体に響く」ことが作品の肝になるジャンルでは、HS-7単体ではローエンドの再現がやや物足りなく感じることがある。
低いところでの、キックとベースの重なりが見えにくい場面があります。
あと、高音がカリカリしていないので、ズンズン・カリカリな感じの派手さはないから、テンションがアゲアゲにならない。
「これ、低音がズンズン気持ちよく鳴ってるのかな?」
「このアレンジで、バイブスMAXのグルーヴ出せているかな?」
「シンセのキラキラが足りないけど、どうなんだろう?」
そんな事が気になることが、よくあります。
そんな時は、別のリスニング環境(ずばり、ヘッドホン)と組み合わせて判断しています。比較的ドンシャリの味付けの聞いたアゲアゲなヘッドフォンで聞いてますね。
でも「見えるものは、ちゃんと見せてくれている」というのがHS-7だと思います。
ジャンルに合った判断軸を持てる人ほど、相性の良さを感じられるスピーカーなんじゃないかな?
まとめ|HS-7はいいぞ〜。買って後悔はしない…でもちょっと飽きるけどね。
YAMAHA HS-7は、派手な演出や耳あたりの良さとは少し距離を置いたスピーカー。
その代わりに、音の本質とまっすぐ向き合える「素直さ」と「誠実さ」を持っていると思います。
生楽器・生演奏系サウンドの様な、“音に真面目なジャンル”にとって、HS-7は信頼できる相棒になってくれるはず。
もちろん、EDMやヒップホップのように低域の体感が重要なジャンルには物足りなさもあるし、設置や部屋の環境によって実力を出しきれないこともあります。
でも、それらを理解したうえで活かせば、HS-7は長く付き合える一本になります!
実際、私も8年使い続けていますし、ずっと信頼し続けています。まじで最強!
そのクセの無さ・無難さが、ちょっと飽きちゃって火遊びしたくなっちゃうこともあるけどね〜。
最近、これとかマジ欲しい↓
でも、そんな時でも「7インチでよかった」と思えます。だって「5インチをサブスピーカーとして買ってもいいかな」という言い訳(?)ができるじゃないですか!
5インチを持ってて、他の5インチを買うとなると「あんた!同じようなの持ってるじゃない!」と家庭内稟議が通らない。でも、「コンパクトなやつも、サブとして必要でありまして…」というプレゼンができる(…可能性がある!)

以上で、HS-7のレビューはおしまい。
購入を迷っている方の参考になれば嬉しいです!
ABOUT
-
"コとネ"と言います。本業はドラマーで、サポートやレコーディング、講師をやっています。
ドラマーだけどDTMerで作曲します。ソフトウェアをいじくり回すのが好きで、セール情報をウォッチするのも楽しい。ブログではDTMの疑問や悩みをメモしています。
Youtube(楽曲用)
Youtube(DTM用)
\ 制作のご依頼はこちら /